特集「景観」座談会
この座談会は,2005年3月4日に,日本測量協会において約2時間にわたり行われました。機関誌『測量』2005年5月号には,紙面の都合上,話題の一部を抜粋して掲載しました。この「測量情報館」では,座談会の話題の全てをお届けいたします。
|
|
ご出席の皆様 (五十音順) |
|
| 伊藤 登 | ㈱プランニングネットワーク 代表取締役 |
| 長濱 龍一郎 | 松下電工㈱ 中央エンジニアリング綜合部 環境計画推進グループ 部長 |
| 福井 恒明 | 東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤学専攻 景観研究室 講師 |
| 政木 英一 | 国際航業㈱ 公共ビジネス事業本部 国土情報基盤推進部 部長 |
| 武藤 良樹【司会】 | アジア航測㈱ 経営企画本部 都市事業推進室 課長 |
武藤【司会】: 本日はお忙しいところ,機関誌・月刊『測量』2005年5月号特集「景観」の座談会にご出席いただき,ありがとうございます。
景観法が昨年12月17日に施行され,公共事業の発注者の考え方が変化してきたと思います。この変化に対して,測量・調査・設計の仕事に携わる私たち技術者は,どのように「景観」と関わっていけばよいかを考えていきたいと思います。本日は,第一線で活躍されている方にお集まりいただきましたので,現場の生々しい状況を噛み砕いてお話しいただき,月刊『測量』の読者に役立つヒントを授けていただければ幸いです。
はじめに,ご出席の皆様から自己紹介をお願いします。
まず,私ですが,アジア航測に所属しており,途中で財団へ出向したり商社の仕事にも関ったりしてきましたが,橋や街路の設計を中心に15年間,公共事業の中でどのような空間を作ったらよいかということを,景観の視点から考えながら仕事をしてきました。
長濱:
松下電工の長濱です。12,13年前からコンピュータグラフィックス分野の仕事を手がけています。その当時,バーチャルリアリティ(VR)技術の民生利用にわが社が一番最初にこぎつけたことから,この技術を意思決定や合意形成に適応したいと考えるようになりました。ご指導を得てきた大阪大学環境工学科の笹田研究室には適用事例がたくさんあるのですが,民間の事業として技術的にも経営的にも確立したいという思いで,業務に邁進してきました。ようやく5年ぐらい前に,意思決定や合意形成のプロセスの中心にVRを据えて議論していくというモデルの雛型ができました。最近では認知度も高まり,実用の中での厳しい評価を受けながら,利用機能等の充実に努めている段階です。
伊藤:
プランニングネットワークの伊藤です。大学では造園関係を学んだのですが,東工大大学院の中村先生のご指導を得てから,一貫して景観に関わっており,計画から設計までひととおりこなしてきました。河川関係の業務が多いのですが,道路や都市などの景観もこなしておりますので,デザインの現場の状況はある程度理解しているつもりです。
福井:
東京大学の福井です。大学は土木の測量研究室出身です。卒業後,清水建設に入って1年間,建設の現場にいました。その後の4年間は景観設計の部署で色々な仕事をやりました。大学にもどってからは,地方のまちづくりを中心に活動しています。測量・GISは専門外ですが,都市計画の場面で測量・GISを扱うことに,余り抵抗感は感じません。
政木:
国際航業の政木です。入社と同時に埼玉大学大学院の社会人コースに入学し,窪田先生の指導を受けて景観の基礎を勉強しつつ,CADやGISを利用した設計支援システムの研究開発にたずさわりました。現在は、国、県、自治体を中心としたGIS導入コンサルタントとして働いています。
最近の測量分野は,測るだけではなく,測った後の成果を空間情報としてどのようにデータベース化するかが大きなテーマになっています。地理情報標準を活用した空間情報の整備や運用方法などを中心にした活動をしています。今日は,デザイナーの方々が必要としているデータをどうやったらうまく作れるかということについてお話しできるかと思います。
1. 測量は,景観デザイナーが求める3次元空間データを提供できるか?
武藤【司会】: 本日の座談会のキーワードの一つが「現場から」です。まず,測量会社の現場のお話を,政木さんからお願いします。
政木: 3次元空間情報がどのようにして作られ,それをどのようにして提供しているかをご紹介したいと思います。測量の成果として3次元空間情報が作られても,自由にハンドリングできるツールが少ない(あっても高価な)ため,なかなか普及していかないという状況です。そこで,私たちはVS-Viewerという3次元GIS(もどき)を開発し,フリーでご利用いただけるようにしました。
これまで3次元GISと呼ばれるアプリケーションの大半は表示機能しかなかったのですが,このシステムには解析機能も備えています。地形に関する3次元空間情報は、TINモデルやDEM(Digital Elevation Model)などの方法でデータを扱うことができます。このデータを活用すると、自由な視点で建物や土木構造物を見ることができるだけでなく(図-1:3次元で見る・自由な視点移動),簡単な解析を行うことで,地形の断面図、傾斜区分図、標高区分図などを作成できるようになります(図-2:3次元で解析する・主題図作成)。
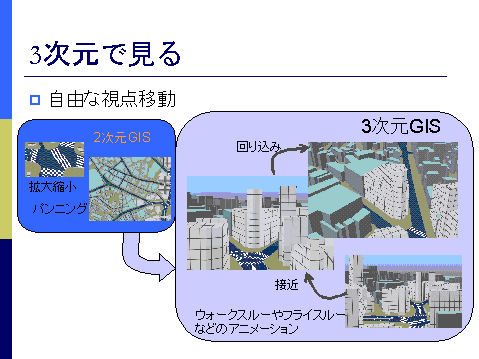
図-1 3次元で見る・自由な視点移動
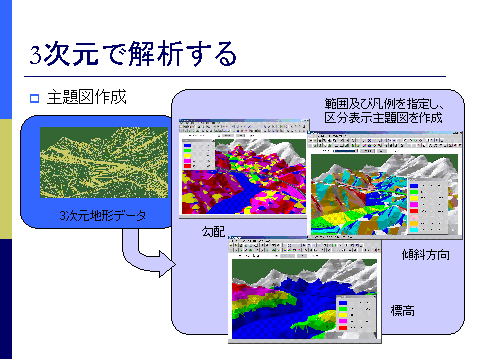
図-2 3次元で解析する・主題図作成
また,地表面だけでなく,地質の3次元構造などもほぼ同様の方法でデータ化することが出来ます。これにより、地質構造の理解に役立ちます(図-3:3次元で解析する・断面図作成)。さらに,地形データとデジタル航空写真を組み合わせたデジタルオルソ画像を作ると,地形データだけの場合とは違った使い方ができると思います。
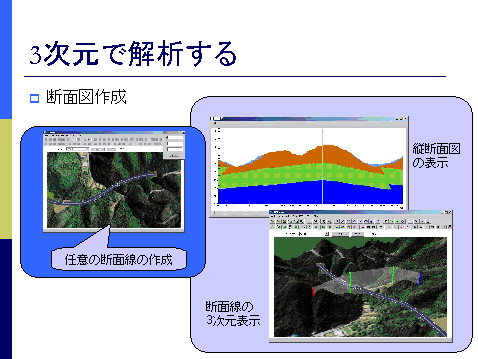
図-3 3次元で解析する・断面図作成
建築の世界で必要とされる建物の中の3次元空間情報の構築も行っています。ここで我々が提案するデータの特徴は,図形の裏側でジオメトリの位相関係を持っていることです。ですから,ある場所から別の場所へ移動する時の最短経路を探すことができます。点と線のネットワーク(いわゆる中心線ネットワーク)による最短経路が一般的ですが、,面と線でもネットワーク解析ができますので,これを使った経路探索も可能です(図-4:3次元で解析する・経路探索)。
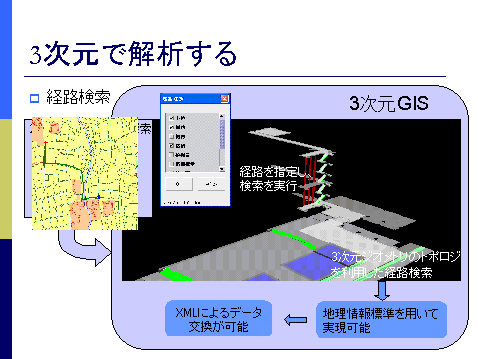
図-4 3次元で解析する・経路探索
色々なデータ構造が作れますので,こんなことをやりたいという要望をいただければ,今までは出来なかったことが解決できるかもしれません。
伊藤: 景観デザインに必要なデータが容易に手に入らず困っています。例えば,道路は建設行政が,交通規制は警察が担当しているため,警察が敷設したものは道路台帳に迅速には反映されていないと思います。同じような例が他にもあり,計画機関から与えられた図面だけでは不十分なのです。信用できない図面さえあります。ですから,自分で必要なデータを集めなければならないのが実情です。3次元空間データを扱ってみたいとは思いますが,2次元データさえままならないという実感です。
武藤【司会】: 2次元データすら怪しいというのは私も同感です。たまたま,古い地図を年代別に並べていたら,変化するはずの無いところが変化したかのように表現されていました。表記の誤りかどうかは分からないのですが,そのまま鵜呑みにして設計に利用していたら,大きな過ちを起こすところでした。
伊藤: お金が1円違うと怒られる銀行と同じで,詳細設計段階では寸法が1mm違うと重大な問題になります。このような誤りは私たちのミスで生じることもあるのですが,信じていた地図に原因があると分かると裏切られたような気になります。
福井: 私がゼネコンで施工の現場にいた時,「既存の図面は疑え」と教育されました。合っている筈がないという意味です。
武藤【司会】: 長濱さんは3次元のVRシステムを使って,街づくりや地域づくりの景観シミュレーションをたくさん手がけられていますが,データをどのようにして入手されているのでしょうか。信用できないといわれる地図データで,住民説明に耐えられるのでしょうか。意思決定・合意形成支援コンサルティングの立場からご意見をお願いします。
長濱: 私どもがお手伝いしている街づくりや地域づくりの景観シミュレーションは,構想の早い段階から計画素案の検討にVR空間を活用していただくようにしています。その段階では,必ずしも高い精度のデータを必要としていません。また従来はある段階の検討案を議論し,まとまってから精緻な3次元CGを作ることが多かったようですが,そのような決着させる段階で「どうもイメージが違う」と言われても,大変な手戻りが生じます。
同じ手間をかけて3Dデータを作るなら,早い段階で,概括的だけれどおよそのイメージが分かるCGを作って,計画者や住民に見てもらい,大局的な議論を重ねます。それを一歩ずつ具体化させてゆけば,到達点のイメージの共有化がされているため,手戻りの無いスムーズな作業がスピーディーにできると考えており,それを可能とするVRを中心とした枠組みをつくりました。大局的なデザインの方向性を議論するときには,それにあったレベルのデータがあればよいわけです。勿論,景観シミュレーションに使える3次元データが容易に入手できるなら使います。またデータが無い場合は,それをその段階の検討に必要十分なレベルでさっさとつくるということです。
政木: 今は,景観デザインに使えるデータが無いため,必要の都度作っていくしかないですが,統合型GISなどのプロジェクトが進められていて,行政などが日常活用する空間情報を電子化して共用しようとしています。道路台帳も電子化する方向で検討が進んでいます。今現在は,これらのプロジェクトで整備される空間情報は2次元です。恐らく,このままでは,景観デザインに直接利用できるデータではないと思います。ただ,今使えるデータが無いから仕方がないと思っていると,5年経っても相変わらず景観デザインのためのデータは整備されないかも知れません。景観計画・評価のためには,こういう構造のデータが必要だ,という声をあげておけば,それが仕様に盛り込まれる可能性がでてきます。景観検討だけを目的にしたデータ整備・定常的維持管理は困難ですが,行政が日常業務で使っている空間情報のデータ構造を,景観検討向けに少しだけプラスするのは,十分に可能性のある話だと思います。それが実現できれば,3次元空間データが国土情報インフラの一つになっていくと思います。(図-5:3次元GISの利用イメージ)
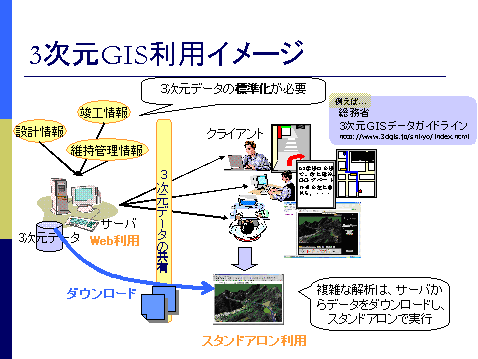
図-5 3次元GIS利用イメージ
福井: 3次元空間データが,まさに1/2500の都市計画白図のような形で使われるようになるのですね。しかしそのためには,扱い易いデータや汎用性のあるオープンなシステムが準備される必要があると思います。その上で,様々な目的に合うように特化した使い方をしていくということになるのでしょうね。
長濱: 大手の航空測量会社は,各社が競い合って同じようなデータを作っておられます。これらは現況を理解したり,計画案との関連性を評価する時に使いたいデータです。国がこれらのデータを買い上げ,重複の無駄を排除しインフラとして整えてくれることを期待します。土木や建築のCGパースを描く業界も実は同じようなもので,使いまわし加工のできるCADデータはお客に納品せず,CG画だけを成果品として納品することがほとんどのようです。そのためいくらCGパースが描かれても,その空間の3次元のCADデータはまったく一元的に管理されていません。3次元のCADデータこそが継続活用を担保できるものだという認識が発注者に乏しかったからだと思いますが,私はこれを変えたいと思っており,発注者の方には,CG画だけでなく3次元のCADデータも成果品として要求するようにしてくださいと申し上げています。
伊藤: 主要な公共物(道路や河川など)を除けば,都市景観の構成要素の殆どが民間施設ですから,建築確認申請の時に電子化データを提出させるようにすれば,木造の住宅の建て替えが一巡する30年後には,都市の3Dモデルができるかもしれませんね。
政木: 都市計画基本図は5年に1回更新されます。最近ではこれを電子データとして作成する自治体が増えています。これを活用して建築確認申請を受けたら直ぐにデータベースを更新すれば,新鮮な3次元空間データを持ち続けることができます。こういう仕組みを作る必要があります。
福井: ところが,縦割り行政の中では,予算も限られ,自分たちの管理が滞りなく行える範囲のことしか考えませんから,とりあえず必要なデータを作ればよいというのが実情ではないでしょうか。
政木: ですから,少し違うセンスの力が外部から働かないと,なかなかそういうデータベースが維持されません。余分な経費がかかるという話もありますが,ツールやデータの価格はニーズがたくさんあれば下がっていきますから,必ずしもコストの増加にはつながらないと考えています。
「そんなこと言ったって仕組みが無いじゃない」とよく言われるのですが,「無いから作れ」と言って欲しい。そういう声がどんどん大きくならないといけない。地震シミュレーションに使うデータモデルは、いろいろな専門家が提案していますが、景観デザインでは,そういう提言をする人がいない。景観評価のためにどういうデータモデルがよいかということを述べている論文も非常に少ない。私たちは景観デザインのための視覚的シミュレーションのニーズ程度は掴めるのですが,それ以外の部分のニーズが分かりません。ですから,デザイナーから,データ整備が必要だということを,もっと発言していただいてもよいのではないかと思います。
3次元空間データが様々なニーズに応えられるようにするには,どのようなデータ構造を持たせればよいかという研究が総務省で行われています。ここでは,3次元GISデータの基本スキーマとして,幾何・位相・時間のような一番根っこにある部分をある程度共通の仕様で定義することにしています。これが実現すると,必要なデータをいつでも調達でき,新たにデータを作る必要がなくなります。
また,カーナビの世界では,業界にいる人たちが知恵をしぼって,自分たちが使えるベースとなるデータ(例えば,道路ネットワーク)を標準化するにはどうしたらよいかを考えています。残念ながら,土木の世界にはそういったことがありません。特に,測量業者は公共測量作業規程に甘んじているところがあって,規程の仕様さえクリアできればよいと考えているところがある。行政任せにするのではなく,ニーズ側の土木とシーズ側の測量が技術の可能性を互いに摺り合わせて,土木の空間データ標準を検討する時期かもしれません。ただ,民間企業が独自で動くのは難しいところもあるので,測量協会のような立
場のところが旗振り役をしてほしい。
福井: Linuxなどのオープンソースのシステムや,ワールドワイドウェブコンソーシアムといった標準規格を作り出すシステムの考え方が,空間データづくりの世界にも要るのではないかという話ですね。
長濱: 工業デザインの世界が3次元CADで設計するのは,単に形を立体的に見るだけでなく,様々な解析や検証に使えるからです。そして,一度データを作ったら,デファクトスタンダード(事実上の世界標準)といわれるフォーマットで残すようにする。いかに互換性のあるデータを作るか,いかに継続的に使えるデータにするかが大切です。これによって,特定システムに依存してしまうという弊害がなくなり,システム間が緩く繋がってくる。それぞれの専門分野のソフトウエアにその空間データが手渡された時に,専門的なエンジニアリングの場面でも使えるという仕組みが,私たちの世界の都市空間データベースでも構築できたらよいなと思います。横断的にデータを流用したいという大きなニーズを阻害しないことが大切だと考えています。
2. GISデータは景観デザインに使えない?
長濱: GISで作った景観デザインの例をよく見かけますが,その殆どが鳥瞰です。景観には,遠景の眺望と,人間の目線から見た街中の風景があるのですが,測量やGISは後者の景観を置き去っている。
青森市さんが検討会や広報に活用されているVR空間をご紹介します。鳥瞰的な視点場(図-6: 青森市のCG画像・鳥瞰画像)は全体像の掌握や単体の全景把握には必要ですが,実際には早い段階から生活者や利用者の目線での検討がより重要です。たとえば,駅広などでの線形検討も,利便性も含めてバスから降りて駅に行く人の目線高さでの検討を重ねます(図-7: 青森市のCG画像・人の高さから見た風景)。人の目に映る事柄やその動的な変化を検討しないと,景観に関することも含め,何か重要な課題を見落とすことになるからです。

図-6 青森市のCG画像・鳥瞰画像

図-7 青森市のCG画像・人の高さから見た風景
CG画面を見てもらいながら,常緑樹よりも針葉樹がよいとか,何メートルぐらいの高さの植え込みがよいとかのレベルの意見を出してもらいます。樹木は大きくなりますから50年後の風景はこんな風になりますとか,季節によってこんな風に見えますとかいったことも検討しながら,意思決定していただくようにしています。
誤解かも知れませんが,国土情報的なデータを用いたデモンストレーションを見ている限りでは,近景のデザインに耐えられるデータ構造を持っていないのではないかと推測しています。GISが2次元データだけでなく3次元データも扱えるようになったので,今まで出来なかった色々なことができると喧伝されています。確かに3次元データの空間的広がりのヒエラルキーが構築されれば,近景にも使える可能性はあると思います。例えば,小さな街づくりの単位で言えば100mぐらいの範囲を対象にするのですが,この狭い範囲の構造化されたデータが準備されていないのではないでしょうか。比喩的な言い方をすると,メッシュ単位のデータを扱うときに,そのメッシュよりも小さな世界に入ってしまえばどうしようもないということです。GISの可能性としては分かりますが,本当にできるところまで徹底的に作りこまれておらず,現場から文句をがんがん言ってくれという段階にまで達していないと感じています。もっとも,これは,私の個人的な印象ですが・・・。
政木: ディテールのデザインのためにGISが活用されていないというのは事実だと思います。ただ,空間データ整備の可能性として考えれば,台帳や完成平面図レベルのデータがどれだけ電子化され整備されるかということに依存すると思います。完成平面図には,点字ブロックのような情報も含まれますので,ディテールのデザインにも使えると思います。
私は,このようなデータ整備は民間の責務だと思っていません。その部分のデータを管理しているのは行政ですから,「行政がインフラ施設の管理のためのデータをどういうレベルで整備しようと考えているのか?」にかかっていると思います。
法律的な義務で各種の台帳類が作成されますが,これが,他の目的で活用されることが少なく(法律上できない場合が多い),データが使い回しできるような形で蓄積されていない。現場でのデータの使われ方と,データをストックする仕組みとが乖離していると考えています。ですから,先ず行政にお願いしたいのは,使い回しのできるデータを整備していただくことです。費用対効果を高めるため,行政以外の人たちも使えるようにする必要があります。こういったことが実現されると,電子化された3次元空間データは飛躍的に発展していくと思います。いずれにしても,ニーズのない分野のデータは情報インフラとして整備されないと思いますから,景観デザインに使える3次元空間データをどんどん作れというべきだと思います。
福井: とても参考になるお話をいただきました。でも気になるのは,青森市のような検討空間としてのVRを作るのにどれくらいの経費がかかるかということです。予算の限られたまちづくりの現場ではVRだけになけなしのお金を使うことは現実的ではありません。
VRを用いたまちづくりのプロセス全体をパッケージした方が,使い手にとっては導入しやすいでしょうね。
長濱: 街のVRデータをつくるには膨大な手間がかかると思われていますが,意思決定・合意形成のためのVRデータは膨大ではありません。どんなに大きなものでも1ヶ月あればできますし,たいていの街づくりであれば1~2週間でできます。それを,景観の検討期間中に少しずつ修正していけばデータは継続的に使えます。GISや航空測量で作ったデータも存在するのは既存部分だけで,検討要素は同じように作りますから,VRが高コストということはありません。
経費面を検討する場合には,どれだけの経費がかけられるかという観点と,どれだけの経済的効果をもたらすかという,両方の観点からみる必要があります。住民を巻き込んだ議論(パブリックインボルブメント)をしないと駄目ですよということが,7~8年前から国土交通白書に出てきていますが,それが実現できたときにどれだけの効果があるかという費用対効果を計っていくべきだと思っています。
とはいえ,景観というソフト面だけの事業になると,地方では予算化が難しいのが実情です。スムーズな意思決定や,事業に対する住民の方々の理解や期待の上で,その事業が行われていく効果を考えれば,全ての事業費の中でソフト部分に多少の経費をかけるだけの価値はあると思っています。これは,売り込む側の言い分かも知れませんが・・・。景観CGやVRを,単にソフト事業の価格という見方をするのではなく,計画者や住民が知恵を出し合う時のコンサルタントに対する代価と考えていただきたいと思っています。
3. データユーザの現場を知ろう
武藤【司会】: 測量会社は,これまでに沢山のデータを作ってきましたが,その殆どは,個々の発注者の事業にだけ使えるデータ仕様になっていました。共有して使い回しできるデータとはいえません。地理情報標準のように共有化を前提にした要求仕様が示されれば,それを作り上げる力が測量業界にはあります。消費財メーカーのように,ニーズを仮定して,データを作って,「さあ,どうだ」というのも,受注産業主体の測量会社では難しいと思います。
長濱さんは,長い年月をかけて合意形成のための講座を開いたりして,景観CGやVBの教育・普及活動をされてきた中で,事業者の意思決定や住民の合意形成のためのニーズを掴まれ,どのような空間データを,どう構築して,どう使えばよいかを理解してこられました。色々な目的に使えるように・・・と,何でもかんでも機能を付ければよいというものではなく,必要な機能だけを付ければよいのだということを体感されています。この辺りのお話をお願いできますか。
長濱: GISの3次元空間データは,それを使いたい人の立場にたって作られているのかなと疑問に思うことがあります。GISは,ユーザインタフェースの一部分としての地図とそれに付属したデータベースからなるものだと認識していますが,そういった意味では非常に多様な活用分野があるはずです。ところがそれをたとえば都市計画という一分野のそのまたある領域に適用しようとしたときの活用条件の想定や,それに必要なつくりこみが踏み込んでなされているのかな,と気になります。
試みに,CG画の後ろにデータベースシステムを作り,CG画の建物や道路に触ると,その建物や道路の諸元が表示され,その諸元をクリックすると図面が出てくるというものを作ったことがあります。このようなことはGISの得意とするところだと思いますので,GISで都市計画を作ったら,その空間データを営繕部門に引き渡して,画面上の街灯がピカピカ点滅すると,そろそろ電球を交換する時期がきたというアラームが分かるようにするなど,分かり易い末端レベルの使い道を広げていく必要があるように思います。
伊藤: デザインのためのデータが欲しいと思って,事業の担当者に「こういうデータはありませんか」と聞いても,出されてくるものには満足できるものがないんです。要求しても,「これ以上は無い」と言われると,われわれはデータを入手するための次の一手がありませんから,与えられたデータでなんとかするか,与えられたデータを補完するものを自分が現場で見つけてくるしかありません。
長濱: それはまさにニーズですよね。
CGではないのですが,以前,「光のまぶしさを検知できないか」という話があったときに,光源に対する目の角膜衝動をまぶしさに代表させて,ある照度を超えるとピカッと光るようにしたものを作り,空港の灯火管制で使っていただいたことがありました。机上で考えてもニーズは分からないが,現場に出るとお客からニーズを与えてもらえます。現場では,「こういうことが出来たらいいのに」「できますよ」という会話が次々とでてきます。
どんなことをして欲しいのかということと,どんなことができるのということが,上手く合致しないから,GISは何に使えるのという話が出てくるのだと思います。
政木: 長濱さんの言うとおり,計画機関の日常的な作業プロセスそのものを,われわれシステムエンジニアへ要望としてぶつけていただければ,どういう使い方をすればよいかが提案できると思います。
製品仕様で空間データを構築する時代になったのですから,これからは,データ提供側のプロとしての自覚を持って,利用者が求めていることを理解できるよう様々な知識を持たないといけない。利用者との議論を通じて,どのような空間データの構造をどのような方法で取得するのかなどの提案を,利用者が分かる言葉で説明し意思疎通できるようにする必要があると感じますね。
使い手側の人は,GISやCGの機能や使い方を全く気にせずに言ってもらってかまわない。純粋な気持ちで,「俺,こんなことを考えているのだが,できるかな」といった会話が必要ですね。
武藤【司会】: 本当によいものを作っているデザイナーやプランナーは,その事業のコーディネータとして,事業が完結するまで(工事が終わった後でも)全責任を負っています。
空間データをどうハンドリングするかということについては,事業の途中の各段階で,責任を負っている方々と色々な話しを詰めていくことが重要だと思います。今までは,測量は測量というように,単独の商売として成り立っていたため,互いに議論する機会が少なかったのですが,これからは測量業や地域住民の方も一緒になって,何が地域にとって大事なのかをそれぞれの立場から知恵を出して考えることが必要で,景観という新しい切り口ができたと理解しています。
4. 景観デザインのために,測量・GISでしかできないこと
武藤【司会】: 意思決定・合意形成をする時,景観を熟知しているプロや,一般の住民でも景観に造詣の深い方であれば,図面を見せれば理解してもらえます。しかし,興味のない人に図面を見せても「分からない」と言われる。地図屋としては悩ましいことで,図面から3次元空間をイメージすることが行われてこなかったからだと思います。このような状況の中での意思決定・合意形成を考えると,図面でなく,CG,VR,模型など臨場感のある表現が不可欠だと思います。
模型というと,どちらかといえば原始的な印象がするのですが,将来的に,模型はCGやVRにとって変わるのでしょうか。景観デザインでは模型をよく作って,構造物の「おさまりがよい」という表現をしますが,CGやVRでも同じような臨場感を感じることができるのでしょうか。
福井: 大学の設計演習では,私は学生にCGやVRを使わずに模型を作れと言っています(図-8:模型を用いた大学の設計演習)。

図-8 模型を用いた大学の設計演習
なぜかというと,景観設計は環境を作る仕事で,小さな空間から,都市全体まで色々なスケールを行き来しなくてはいけない。デザイナーやプランナーにとってはそのスケール感覚を磨くことが非常に重要なのです。今のVRの問題点は,スケール感が掴みにくいことです。VRを見て,さて何メートル歩いたでしょうと言われても,正確に答えられない。景観をデザインする立場の人間は,何時でも大小のスケールを自在に行き来して作業する必要がある。ですから,GISやCG,VRは,根本的に模型の代りにはならないと思います。
しかし,模型といっても2種類あって,一つはデザイナーが自分自身と対話するためにスケッチするような気分で使うスタディ模型,もう一つはパブリックインボルブメント等に使うプレゼンテーション用模型です。後者については,景観コントロールの効果検証など,分野によっては模型よりもGISやCG,VRの方が便利で効果が高いと思います。
武藤【司会】: 伊藤さんが阿武隈川のデザインを担当されていた時,地元の方が「どこをデザインしたの。もともとあった川じゃない」というコメントがあったのをよく覚えています。伊藤さんの阿武隈川水辺空間デザインは,模型を作って検討されたのでしょうか。
伊藤: 阿武隈川の水辺空間の事業は,模型を作らず,殆どのデザインを現場で行いました(図-9(a)~(f):阿武隈川渡利水辺の楽校)。

図-9(a) 阿武隈川渡利地区全景

図-9(b) 阿武隈川渡利地区・高水敷

図-9(c) 阿武隈川渡利地区・園路と樹木

図-9(d) 阿武隈川水系荒川・緩傾斜堤防

図-9(e) 阿武隈川御倉地区

図-9(f) 阿武隈川御倉地区
日本庭園のデザイン手法の特徴のひとつは,自然がつくりあげる形を詳細に観察し,そのプロトタイプをつくり,それを洗練させて庭園の中にとりこんでいくというものです。縮景ということばは,実際のスケールの景観を庭園のスケールに縮めて収めることによっています。阿武隈川の例は,それを実スケールで,現場での空間の認識を重視して行ったものです。ダムなどを作るときに大きな模型を作るのは,なるべく肌身で感じようと努力しているからだと思います。ですから,私も,模型が,GISやCG,VRに置き換わることはないと思います。
また,大抵の景観デザイナーは,工業デザイナーと違って,自分ではCGを扱いません。ここをこんなふうに変えたいと思った時に,紙やすりで削ったり,カッターで切ったり,ということがCGでは出来ないのです。デザインはモデルをひねくり回すことに頭を使っていますから,データ入力に頭を切り替えると,イメージ思考の回路が切れてしまいます。
武藤【司会】: かつて,3次元データを駆使して微地形を表現しようとしたことがあります。結果的には3次元データでは微地形が表現できず,図面もコンター線しか使えないので微地形を上手に表現できなかった。最終的には,現場に座り込んでスケッチすることにしました。デザインは頭で考えて,作業は自分の手足を使ってやりたいですよね。デザインを考えているのと同じ頭を使ってデータ入力なんかできませんよね。
福井: GISの強さは,数値で表されているものは,きちんとした形になり,嘘をつかないところだと思います。その利点を生かすには,デザイナーが頭を使わなくてもよいように,徹底的に使いやすくする必要がありますね。
伊藤: 道路のCG画面をみながら,「ここはもう少しRをきつくするといいな・・・」と念じていると,Rがきつくなってくるようなものがあればいいのですが・・・。(それ,いいですね。笑)
政木: オペレーションは,今はマウスを使うしかないのですが,VRの世界で実験的にやられている,手袋の形をした電子グローブを使ってみましょうか。
福井: 電子グローブがよいかどうか分かりませんね。そこまでやるなら,まだ手の方がいいかという感じもします(笑)。
GISが模型やCG,VRと競い合うのではなく,GISでなければ出来ないような「デザインの手がかり」が掴めないでしょうか。研究室の学生が景観地層図という論文を書いたことがあります。これは,その場所の景観の変遷を時空間表現したもので,その地域では何が重要な景観要素なのかを読み取れるようにした図です。当時は,まだ手書きのOHPシートを重ねていたのですが,情報を重ねると解ってくる景観要素の分析ツールとして,CG・VR・模型とは別の土俵でGISの特徴を活かすことができると思います。
伊藤: 地質分類図や植生図など様々な図面があるのですが,重ねて見れないですね。今までは重ねて見れるように図面を書き起こしていました。例えば植生と地質の関係を調べるため,透過的に重ねて見ることはGISの得意分野なんでしょうね。
長濱: 松江市の景観計画区域を指定するためのワークショップで,住民の方々に街歩きをしていただき,好きな場所,嫌いな場所を選んで写真を撮ってもらいました。その写真を整理しながら風景のコメントや属性を言葉で表現してもらい,白地図上に貼り付けました。似た言葉に同じ色を与えるという作業をしているところを住民に見せることで,「こういう考え方でまとめていっている」という共通認識ができます。デザインをいきなり見せるのではなく,考え方を共有しながら概念をデザインに置き換えていくことをやってみたいと思っています。こういうのも,GISの得意分野の一つかもしれませんね。
この事例では瓦屋根や城壁のように,良いと思う景観要素が発見できたら,VR空間の中で,色瓦が使われると風景がどう変化するか,高い建物ができるとどうなるかというのを話し合ってもらいました。つまり同じVR空間の同じ映像をみながら同じレベルで理解していただいているので,ひとりひとりの意見を出し合うことがスムーズにできました(図-10:松江市CG画像)。

図-10 松江市CG画像
福井: 私もワークショップをやるときには,地図の上に付箋をはりつけていきます。それを電子化しただけではGISやCGを導入する意味が無いので,色々な分野・専門・年齢・地域の人が,同じシステムにアクセスしながら,意見を取り纏めていけると面白いですよね。
長濱: 複数の端末からアクセスする技術は,別の事例で実現されています。空港の消防隊員は,各自の役割を分担しながら1台の飛行機を消火するのですが,そのために作成したVRは,別々の端末から1台の飛行機の消火作業ができるようになっています。
私としては,色んなご意見をいただきながら,少しずつやっていけたら良いなと思っています。街づくりの門外漢なのに,良くやっているなと思っていただけたら嬉しいです。
本当の現場にもぐりこんで,そこで何が行われているのかを知った上で,システム側からのアイデアを次々と出させていただきながら,採択していただいたものだけを使ってもらえればと思っています。
政木: いろいろな視点から見たり,データを重ね合わせて,ある特徴を見つけたり分類するのはGISの得意とするところです。今後も,GISをVRとして使うことは,多分,無いでしょう。GISを使うのなら,多変量解析に空間的な要素も入れて,特徴を抽出したり分類することを考えた方がよいと思います。
例えば,先ほどの長濱さんから紹介された松江市の例のように,沢山の風景写真を集めて,それぞれの写真に写っている内容を分類整理して,その街は景観的にどのような評価を受けているのかを調べてみると,同じような風景なのに違った評価を受けていることがありますよね。そういったことに興味のある景観デザインの研究者がおられれば,GISは有効に使えるのではないかと思います。
GIS(Geographic Information System)は,デジタル地図とデータベースをリンクさせて,コンピュータで取り扱えるようにした地図と理解していただくとよいと思います。人の住所,公共施設の設置場所,事業計画等の計画区域などの情報を,位置情報をキーとして関連付けてデータベース化したものです。
機能は,位置と関連付けられた属性情報を見たり,内容の異なる地図を重ね合わせたりすることによって,複数の情報が取り出せることです。今ではGISが大学の受験問題に出てくるほどで,ようやく市民権が得られるようになりましたが,ここに来るまでには10年近くかかりました。
必要なものは,パソコン,ディスプレイ,プリンタ,ネットワークサーバといったハード類,地図情報とデータベースを扱うソフト,そして,地図情報データです。GISの普及につれて,公共機関では,情報活用能力のある人の育成に力が注がれるようになってきました。
武藤【司会】: 「美しい国づくり」の中で景観事業が推進され,事業別の景観アセスメントガイドラインが検討されているところです。このガイドラインの中で,景観の評価軸や基準が定義されれば,空間データを作る側と利用する側とは齟齬の無いコミュニケーションができるのではないかと期待しています。ひとつのテーブルを囲んで,こうやればいいんじゃない・・・というような会話ができると思います。
伊藤さんに座談会への参加をお願いした時,「景観の意味が重要だよね」とおっしゃってましたが,人によって景観の捉え方はまちまちだと思います。評価のガイドラインがどのように設定されるか高い関心をもっています。
このガイドラインができるとデザインの枠組みがクリアになって,ある意味ではよいことだと思う反面,デザイナーの個性的な自由な発想の妨げにならないのかなと思っています。ガイドラインによって,デザイナーの発想法は変わるものでしょうか,また,景観のプロでなくても,ガイドラインに沿ってやれば,ある程度のことができるようになるのでしょうか。
伊藤: 殆どの景観デザイナーは,ガイドラインができたからと言って,自分の発想スタイルを変えようとは思わないでしょう。デザイナーは,自身の信念や考え方によって,場所の歴史,現状の景観,住民ニーズなどを総合して,デザイナーとしての答えを出しています。ガイドラインが出来たからといって,それに合わせて立ち居振舞いをしようというデザイナーは基本的にはいないと思います。それがプロのデザイナーだと思っています。
一例をあげれば,住民合意で決められた形や色が美観的に正しいかどうか怪しいと思います。歴史・文化・地形などを考えた美しさを追求するところに,デザイナーの職能の発揮の場があります。でないと,住民が決めたからいいんだということになってしまい,景観が良くなるとはとうてい思えません。デザイナーはデザイナーとしての責任と,何にも動じない信念を持つ必要があると思います。
長濱: 住民が「ああ,これはやっぱりすばらしい景観だ」と合意しても,それは大勢の人が「そうだ」と答えた代表値であって,そこには街の個性が出てきません。同じ形容詞の同じような街が,あちこちに出来てしまうことになる。それよりも,その街のその時々の課題をきちんと評価できる機能を作り,その課題の解決を一つずつ積み上げていくことが大切だと思います。そうすると,やがて,使える評価軸の集合体になると思います。
政木: 景観を感覚的に捉えるだけでなく,もう少し工学的に捉えられないものでしょうか。公共空間の景観を作るのですから,景観の下支えになっている要素を一定の基準や尺度で捉えて,この場所の性格はこうだというのを視覚的・人間工学的な視点で議論してもよいのではないかと思います。例えば,ある形を見たときに視覚的に人間はどういったインパクトを受けるかというのを統計的に調べるといった工学的捉え方もできると思います。
これは,デザインの良し悪しという問題ではなく,景観の最終決定をするデザイナーを支援するものだと考えています。
また,景観評価のガイドラインが無いと,ベースになる情報として何を用意すればよいか分からなくなってしまう。根本のところが揺らいだまま,ずっと続いてしまうと思います。なんらかの拠り所になるものがあってもよいのではないかなという気がします。仮に,日本国土に共通の景観指標(百名山が見える国土の範囲といったような)があって,その上で景観デザイナーが地域の個性を生かすことを考えるようになると,データ提供者である測量技術者は,その基本指標の評価に耐えるデータ構造やそれをシステムとして組み込むことを考えるようになります。
福井: 公共性があるから客観的な評価指標が欲しいという気持ちはわかります。長濱さんや政木さんがおっしゃるように,景観のある側面を評価する指標は可能だと思います。
しかし,よい景観を作る上でもっとも重要なのは,要素を構成し,総合化する段階です。
そこは計画者が総合的に判断し,責任を取るしかありません。指標化しなければ評価できないというのは,よい景観についての教育が戦後から最近まで全く行われて来なかったことのツケでしょうね。こうなると,よい景観に関する共通認識や常識をあらためて蓄積するしか道はない。その時に,よい景観の事例(例えば土木学会デザイン賞の受賞作品
http://www.jsce.or.jp/committee/lsd/prize/)のデータをGISやVRの技術を用いてアーカイブ化し,誰でも参照できるようにしておくことは有効だと思います。
伊藤: ドイツには景観の細かい規則や基準があって,私生活面でも守らなくてはいけないルールがあります。ドイツ在住の日本人の方にその点について,ドイツの方はどう考えているのかについてお尋ねしたことがあるのですが,「美は教養の問題であって,美の根源はギリシアに続いているという理解だ」と言われました。
武藤【司会】: ドイツではそうでしょうね。一神教において,「神に仕えている人工物はきれいにつくれ」というのが教えですから。でも日本は・・・。
武藤【司会】: 私たちは,公共測量作業規程というマニュアルに書かれたプロセスに従って測量すると,所期の精度仕様の成果ができるという世界でずっと育ってきました。マニュアルがあればきちんと仕事のできる技術者集団です。マニュアルは無いが街づくりプランのための空間データを作れ,と言われても簡単にはできない。
政木: 測量技術者はマニュアルに慣れすぎたため,事業の目的によっては必要でないものまで作ってしまうという性があります。その結果,いたずらにデータが重くなってしまい,使う時には非表示にするのに時間がかってしまう。ユーザーの世界が求めていることが分からない測量技術者は,頼るものが公共測量作業規程しかないのです。
福井: 書かれたとおりに作ればよいというマニュアルも,性能規定に移りつつあります。
性能が一定の水準をクリアすれば,どのような作り方をしても良いという風に動きつつあります。
政木: 仮に性能規定になったとしても,その規程に頼ってしまうような気がします。データを提供する側のプロとして自覚を持って,クライアントが求めていることを理解できるように,もっと利用分野の知識を持たなければいけない。自分達の責任の中で色々と考えて,このデータは必要ないではありませんかというような提案を,クライアントが分かる言葉で説明し意思疎通ができるようになる必要があります。
測量技術者とデザイナーが1対1の関係の中で,どのようなデータをつくるかを決めて仕事することがあってもよいのですが,それでは対応する技術者によってレベルの差が出てしまう。それを防ぐには,データ構造や品質などを規定した標準仕様が必要だと思います。標準仕様があると,それに追いつく努力をどこの測量業者もやるし,そのスキルを持っています。
そのような仕様を作って従うようにすると,技術がある程度のレベルになると思います。
その上で,デザイナーと話し合い,個別課題に対応してチューニングされたデータを作るという仕組みが作れればよいと思います。最近の空間情報セミナーを覗いてみると,地域の測量業者からも結構参加されていました。どこの会社もレベル向上の意識はありますから,デザイナーのニーズに対応できると思います。
武藤【司会】: 会社の規模を問わず,測量業の多くが設計も行っています。しかし,殆どの設計は,測量の延長線上にあるもので,マニュアルに書かれているとおりの構造計算をし,図面の線を引くという仕事です。景観整備についてもマニュアルやガイドラインで自分達はこうやればいいんだということが分かれば,測量設計業の新しい展開に繋がるという期待がありますが・・・。
伊藤: マニュアルに従って,ある一定水準以上の設計図面ができるというのはとても大事なことです。そういう技術がないと,デザイナーは安心して仕事ができない。ただ,設計マニュアルには形を規定している場合と規定していない場合がある。また,性能試験をクリアすればよく,形までは決められていないものもあります。例えば,水路ならば水は滞留することなく流れる必要があるけれども,水路の線形が直線でなければならないとか,農道と水路が並行でなければならないという規定や法面の勾配が一定でなければならないという規程はないでしょう。
景観デザインの世界に入れるかどうかのポイントは,決められていない部分にどのような答えを出すかであり,マニュアルや標準仕様でやってきたことを一歩越えられるかどうかです。測量設計業の方が,法面を一定勾配でないようにすると柔らかな形になって此処の農村に合うかもしれないと考えるようになれば,地域景観の向上にすごく貢献できるようになると思います。また測量設計業の方が,都市計画プランナーやデザイナーと同じように事業への思いを馳せられるようになると,仕事の内容も変ってくると思うのです。
長濱: 過去の土木の世界ではデザインについては余りうるさくなかったのですが,これからは,景観に配慮したというのが全ての事業の条件になります。マニュアルの世界では困る,というように変化しつつありますね。
伊藤: 測量協会の目的の一つに測量技術者の向上があるのですから,よいデザインの線形の道や水路などを見てもらう景観配慮の講習会を開催してはどうでしょうか。「景観測量講座」とでも名付けましょう。
武藤【司会】: 本日の座談会は,景観デザイナー対データ提供者,測量・GIS対CG・VRのバトルになりましたが,現場の切実な悩みとともに,その解決の糸口になる沢山の話をいただきました。そういった議論の中から,測量と景観との関りを表現する「景観測量」という新しい言葉が生まれました。これを,座談会の参加者全員のコンセンサスとして推進していきたいと考えます。本日は,ありがとうございました。

【ご出席の皆様のプロフィール】 (五十音順)
| ■ 伊藤 登 | ||
 |
◇現職 | ㈱プランニングネットワーク 代表取締役 |
| ◇主な経歴 | 1984年 東京工業大学大学院 社会開発工学 専攻修士課程修了 1984年 清水建設㈱入社 1989年 ㈱プランニングネットワーク設立 |
|
| ◇主な資格 | 技術士(建設部門) | |
| ◇主な受賞 | 2005年 土木学会デザイン賞 2004優秀賞 渡利水辺の楽校 2003年 水辺のユニバーサルデザイン賞 準 大賞/渡利水辺の楽校 |
|
|
◇主な参画 プロジェクト |
山形県県土景観ガイドプラン 山形新都市まちづくり基本計画 阿武隈川渡利地区(福島市)水辺空間デザイン 高湯第1ダム等ダムデザイン 砂鉄川堤防デザイン 仙台市都市再生プロジェクト 他 |
| ■ 長濱 龍一郎 | ||
 |
◇現職 | 松下電工㈱ 中央エンジニアリング綜合部 環境計画推進グループ 部長 |
| ◇現在の活動 | 環境計画支援VRを用いた意思決定・合意形成支援コンサルティング | |
| ◇主な業務 | 大阪大学工学部環境工学科との共同研究において環境計画支援VRシステムを開発し(1998),土木計画事業において,その活用によって 意思決定や合意形成を促進する業務分野を確立。このような手法を,景観評価はもとよりPIにおける計画確認のスタンダードにすべく活動。実績は100件以上。 |
| ■ 福井 恒明 | ||
 |
◇現職 | 東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 景観研究室 講師 |
| ◇現在の活動 | 都市景観やまちづくり(長崎県対馬市や三重県鳥羽市などのまちづくりに従事) | |
| ◇主な経歴 | 東京大学大学院 土木工学専攻修士課程修了(景観研究室) 1995年 清水建設(株)入社 南風原高架橋 (沖縄県)建設現場勤務,本社土木 設計部にて土木構造物全般の景観 デザイン業務 2000年 東京大学大学院助手 2005年より現職 |
|
| ◇その他 | 土木学会景観・デザイン委員会委員兼幹事,土木学会デザイン賞選考小委員会主査 土木学会土木史研究編集小委員会幹事 国交省中部地方整備局景観法活用研究会 委員 景観デザイン研究会運営幹事 |
| ■ 政木 英一 | ||
 |
◇現職 | 国際航業(株) 公共ビジネス事業本部 国土情報基盤推進部 部長 |
| ◇現在の活動 | 公共事業における情報共有のための仕組み構築公共事業におけるライフサイクルデータマネージメント 地理情報標準の普及と実装 |
|
| ◇主な経歴 | 国際航業(株)に入社。埼玉大学大学院 理工学研究科 博士後期課程(社会人コース)修了。在学中に景観評価のための支援システムについて研究。その後,公共事業におけるGIS,CAD,CGを利用した支援システム開発などを経て,現在に至る。 | |
| ◇その他 | 土木学会 情報利用技術委員会 設計情報小委員会 副小委員長 地理情報JIS原案作成委員会 地理情報JIS原案作成・地理識別子による空間参照分科会 主査 ISO/TC211国内幹事会 幹事 (財)データベース振興センター H16年度LBCS本委員会 プロトコルWG 委員 |
| ■ 武藤 良樹 | ||
 |
◇現職 | アジア航測(株)経営企画本部 都市事業推進室 課長(都市基盤デザイン担当) |
| ◇現在の活動 | 公共事業におけるPI支援VRシステムを活用した事業構築支援 公共空間の再生・活用などの受託業務を実 施(景観試行事業など) |
|
| ◇主な経歴 | アジア航測に入社以来,一貫して道路・橋梁の設計に従事。(財)道路環境研究所に出向して道路事業に関わる景観・環境問題についての事業構築・支援。三井物産(株)に出向して空間情報事業の構築。現在に至る。 | |
| ◇その他 | 土木学会 情報利用技術委員会 交通基盤情報ビジネス小委員会 道路空間利用ビジネス分科会 主査 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<特集「景観」編集小委員会>
■委員長 土居原健 月刊『測量』編集委員(アジア航測(株) 総合研究所長)