特集「環境」座談会
この座談会は,2005年10月30日に,日本測量協会において約2時間半にわたり行われました。機関誌『測量』2006年1月号には,紙面の都合上,話題の一部を抜粋して掲載しました。この「測量情報館」では,座談会の話題の全てをお届けいたします。
|
|
ご出席の皆様 (敬称略)
|
|
| 川窪 一郎 | 西日本コンサルタント㈱ 技術部 環境課長 |
| 酒巻 裕三 | 酒巻技術士事務所 代表 |
| 赤土 攻 | アジア航測㈱上席執行役員技師長, (社)自然環境共生技術協会専務理事 |
| 原 慶太郎 | 東京情報大学 総合情報学部 環境情報学科 教授 |
| 瀬戸島 政博 | 月刊『測量』編集委員会副委員長, 国際航業㈱ フェロー役員 |
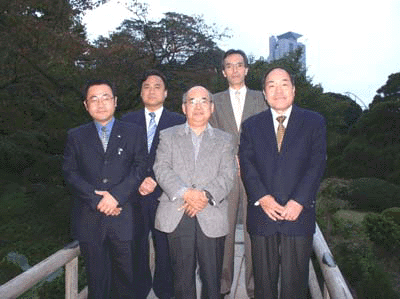
瀬戸島【司会】: 測量技術は,環境の調査解析で数多くの貢献をしています。また,位置と時刻を主キーとする環境情報の一元管理の面で,測量・計測が環境分野で果たす役割がますます高まっています。さらに,グローバルな環境変化が進む中,空間的な広がりや変化を見極めることが強く求められており,時空間を測る測量はさらに重要になってきています。
そこで本日の座談会は,これまでの測量が環境分野で果たしてきた役割や貢献を多面的にレビューしつつ,そこに横たわる課題を明らかにしながら,これからの測量に求められる技術は何か,測量が参入可能な環境領域は何か,必要な人材育成はどうすべきか,などについて議論し,これからの時代の「環境測量技術者」のあり方を提言したいと考えています。
1.測量は環境問題に貢献しているか?
瀬戸島【司会】:
まず,本日の座談会にお集まりの方々から,自己紹介を兼ねて,測量が環境分野で果たしてきた役割や貢献についてお話しいただけますでしょうか。
川窪: 本業は化学プラント屋ですが,今は,大分・宮崎を拠点とする測量・建設コンサルタント会社で環境の仕事をしています。
まず,地域の測量・建設コンサルタント会社の実情を申し上げますと,従来型の公共事業が減少している中,一番初めにあおりをうけるのは測量です。そこで,企業の生き残り策として,各社とも新しい分野へのシフトを模索しており,その一つが,環境分野への進出です。
しかし,ひとくちに環境と言っても,自然環境や社会環境など,対象とする範囲が非常に広く,また,生物環境などはマニアックな部分があり,非常に深い世界でもあります。ですから,これまで土木の分野で測量をしてきた技術屋が,次は環境だと言われても,なかなか対応し難い部分があります。中小企業では人材的にも限られますから,何でも屋にならざるをえず,技術屋が苦労しているところです。環境アセスメントひとつを例にしても,調査,計画,予測評価,保全対策,住民への説明といった一連の流れに対応できる能力が求められますが,それを一人の技術者が対応しなければならないことも多く,チームを組んで,それぞれの専門に分化した作業を行う
のが難しいのが実状です。
測量の環境への貢献ということですので,私どもが行った一つの例として,測量データ等の各種の環境データを基に,GISを利用して解析を行った環境影響評価の実証実験(平成12年度)を紹介します。この実験は,大分県内にある河川流域の水環境を数値的に総合評価する河川水質環境管理計画支援システムを構築する上でのデータ検証に関するものです。まず,地形傾斜,土地利用,降雨データ,土壌データなど様々なデータを用いて,保水機能,土砂崩壊防止機能,土壌浸食防止機能,植生自然度,大気浄化機能,洪水緩和機能,陸域生物生息環境指数(図―1),オオサンショウウオ生息環境,観光資源分布の9つの個別の環境機能を評価式を用いて評価しました。この個別環境機能を,災害防止機能,環境調整機能,生物多様性の3項目に集約し,更に,流域環境保全機能の総合評価を行いました(図―2)。
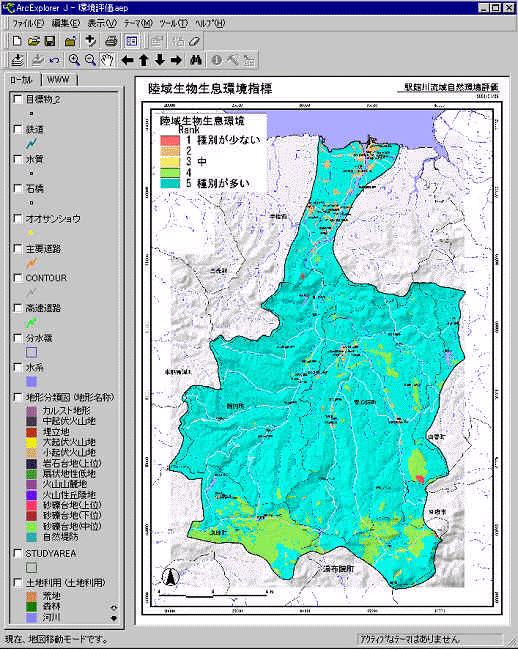
図-1 大分県内の河川水質環境管理計画支援システムのために作成した
陸域生物生息環境指標 (提供:西日本コンサルタント㈱)
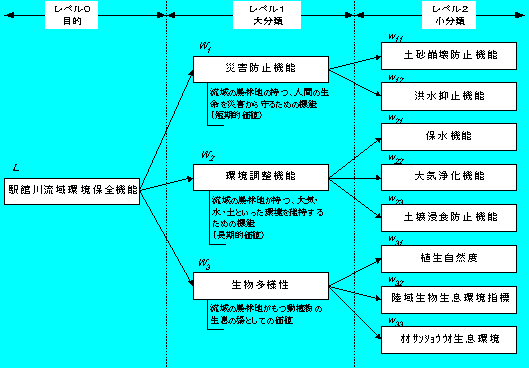
図-2 AHP法による流域環境保全機能の総合評価
(提供:西日本コンサルタント㈱)
評価には,計画者や住民からみた流域保全に対する重要度によって加重演算するAHP法(Analytic Hierarchy Process)を用いました。この評価のためには様々な種類のデータが必要ですが,公的機関の調査データが提供されない,また,データの品質が統一されていないという大きな壁にぶち当たってしまいました。
同じような事例ですが,平成13年度にはGISを用いて土地改良事業のための田園環境マスタープラン策定業務支援システム開発を試みました。農村の自然環境保全に関する指針を,自然環境調査等を踏まえて,地域住民の合意形成を図りつつ作成するもので,これにGISを活用する実験です。各種のデータを用いて,自然環境特性図,生産環境特性図,生活環境特性図を作成し,それらを用いてマスタープラン図を作成する試みです。こちらも地形,緑化地域,水道水源,遺跡,鳥獣保護区他の環境データを必要とするのですが,公共機関の行政目的や教育機関の研究目的には提供されても,民間企業だからという理由で行政の環境データを提供してもらえませんでした。また,提供されてもデータの品質に問題があって使えず,最終的にはシステム構築を断念せざるを得ませんでした。
申し上げたいことは,この2つの実証実験のように,環境を数値の点・線・面の地図データとして取り扱うことができるようになった測量(空間情報)の貢献は大きいということです。しかし,環境評価に必要な環境データの取得および利用について,いくつかの教訓を得ました。一つは,環境データはナイーブな側面があることです。動植物の場合には盗掘の恐れ等がありますし,利害にからむ行政の詳細情報は非開示であり,住民基本台帳情報のような土地に付随した情報は個人情報保護の観点から非公開です。そのため,必要なデータが入手できないという課題があります。二つ目は,各省庁・各市町村において,データ自体が分散化されており,統一的な形で整備されていないことです。そのため,どこに,どういうデータがあるのかが定かでなく,殆どのデータが相互に利活用されていない状況です。このようなデータに絡む問題の解決に,測量と環境の接点があるように思います。地域データの管理には,測量が培ってきたベース技術(位置を主キーにして空間情報を扱う技術)が必要です。
酒巻: 私は,30数年前から,測量・建設コンサルタント会社で環境の現場の仕事をやってきてきました。今は,長野県に拠点をおいて環境コンサルタントをしています。木曽川流域の魚の生息地を保護するため,環境を植物社会学的な手法で評価し,生息している場所と新しく代替地に予定されたところとが均一な環境になっているかどうかを調べる仕事や,長野オリンピックの環境影響調査で,猛禽類の生息率が高い予定地の代替地探しをやりました。この猛禽類の調査方法をもとにして,長野県の猛禽類調査マニュアルを作成し,今も色々な環境コンサルタントに使っていただいています。
それらの環境調査のいずれも,まず現場に入ることから始めています。現場の調査の中で得た経験やノウハウをもとにして手法を考えたり,それをマニュアルにしてきました。環境の領域は多岐にわたりますので,現場に入って環境の課題はなんだろうと考えます。特に長野県内の市町村のように,小規模地域の環境問題では現場重視の調査を行います。関係する色々なデータは,市民を組織化して調査します。子供たちの環境教育の一環なのですが,「どうも最近はカタツムリが減っているね」なんて話をすると,毎年子供達が調べてくれます(図―3)。
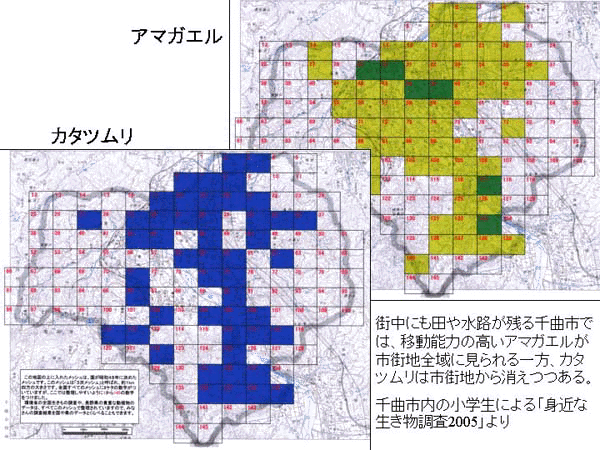
図-3 長野県千曲市の身近な生きものの調査・アマガエルとカタツムリの分布
(提供:酒巻技術士事務所)
そうすると,カタツムリが街の中からほとんど消えているということを子供達が気にかけるようになります。今は,千曲川の川原のジャコウアゲハの生息地の保護活動を,地元の住民や子供達と一緒にやっています。ジャコウアゲハの唯一の餌で,県のレッドデータブックの絶滅危惧種に指定されている多年草ウマノスズクサの保護活動を展開しています(図-4)。

図-4 長野県絶滅危惧種ウマノスズクサとジャコウアゲハの保護活動
(提供:酒巻技術士事務所)
しかし,ジャコウアゲハの生息地がここにあるというようなことは,行政のデータには書かれていません。行政が蓄積している環境情報は,かなりラフで,本当に必要な情報が欠けているのです。
また,国土交通省が提案した千曲川の河川整備計画に対し,市民側から別案が出されましたので,昭和50年撮影の航空写真で当時の河川状況を調べ,当時の湿地の場所や,流入河川の魚の溯上を根拠にして,整備する場所の変更の意見書を国土交通省に出しているところです。行政は,蓄積している環境情報をもとにして机上で計画を立てますので,現場の実態が正しく認識されていません。また,環境はどんどん変化しているのに,データが追いついていないことがあります。
私は地方におりますので,計画機関から,ダム建設工事を発注しようとしているのだけれど,ちょっと行って見てきてくれと頼まれることがあります。そして,現場を見ると,ダム予定地のところが一面のタカゾデソウがあったり,ヒメギフチョウの生息地だったりします。どうしてこんなことになるのかというと,河川水辺の国勢調査や渓流調査が行われ,報告書も出ているのですが,なぜか,そういう繁殖地の記載はないんです。
同じようなことが先日もありました。上信越国立公園の中の池のヒルムシロがかなり繁殖しているので,環境省の了解を得てその除去作業が行われていました。ところが,その場所は非常に珍しいシャジクモの繁殖場所だったのです。けれども,環境省も県も委託されている市も,その資料を持っていないのです。
こういった問題を,環境情報はどう解決していくか。また,その環境情報をどのように皆で共有していくかが,いつも感じる課題です。
赤土: 環境省を30年間勤めた後,民間の測量・建設コンサルタントに勤務しています。また,昨年設立された(社)自然環境共生技術協会の専務理事をしています。自然環境分野で測量が不可欠な植生図作成と自然環境共生事業について話します。
環境省は,自然環境保全法(昭和47年制定)に基づいて,日本の自然環境の全てを把握するため,自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査と呼ばれています)を実施しています。その目的は4つあります。一つは,全国的な観点から自然環境の現状を的確に把握することです。陸域・陸水域・海域の3つの環境分野に分けて整理され,生態系や遺伝的観点からの調査も行われています。二つ目は,概ね5年ごとに自然の時系列的変化を把握することです。三つ目が,調査結果の公開と自然環境のデータバンクの整備で,データはGIS化されて情報提供されています。環境省の生物多様性センター(富士吉田市)には国土地理院の方も出向され,ここで情報化され,提供しています。四つ目は,国土利用計画・環境基本調査・自然環境保全計画などの各種計画策定や,平成9年に法制定された環境アセスメントの基本資料として提供するという役割を担っています。
この調査の主な成果が植生図で,地域の自然環境の状況を把握する一つの基本指標となるデータです。この植生図は,昭和48年に1:200,000植生図(県別),昭和53年~62年に1:50,000植生図(1287面)が作成されました。そして,平成11年から1:25,000植生図の作成に着手し,現在1/3の地域が整備され,現在も継続中です。調査が完了した所から順次GIS化され,平成16年度から公開されています。この植生図の作成には,航空写真や人工衛星画像など,新しい測量技術が駆使されてきました。現在,特に都市周辺の改変の激しい地域の里山・里地の保全が重要課題になっていますが,その改変状況を把握するため高解像度衛星画像写真を用いる計画が進められています。
1:50,000植生図(現存植生図)は,都道府県に委託して作成されました。昭和46年の環境省設立後,昭和47年に各都道府県に環境部が設置され自然保護課ができました。当時は,各役所にも植生の専門家がおり,各地方大学に植生の研究室がありましたので,役所と大学が連携して植生図(アナログのカラー印刷図)を作ったのです。ところが,環境アセスメントにこの1:50,000植生図を利用しようとすると,様々な問題がでてきました。基図にした1:50,000地形図が現況に合わなかったことや,各地の大学の指導で作ったため均一性に欠け,県境では植生図が整合しないんです。
そのため,平成11年からは,1:25,000地形図を基図にして,環境アセスメントに耐えられる精度の高い植生図を作ろうということになりました。ところが,実施体制を作る段になって重大な問題が生じました。役所に植生の専門家がいなくなったのです。また,各地方大学の植生の研究室も無くなってしまったのです。植生が研究の対象で無くなったということです。都道府県への委託ができなくなったので,民間法人いわゆる環境コンサルタントの力を借りて,専門家の助言を仰ぎながら実施するという体制が作られました。作成方法ですが,平成11年~14年の間は,均一性を高めるため空中写真判読を行い,現地で組成と優先種を調査して,約600の全国統一凡例の植生原図を作成しました。つまり,写真判読で相観を把握して地域差を無くし,現地調査によって細かいところを調節するという方式をとりました。精度の上では満足できたのですが,制作に多大の労力を必要としました。そこで,予算節約のためにも効率のよい調査方法が求められ,デジタルオルソ画像による群落の判読や,現地調査や判読の結果を直接オルソ画像上で整理する方式に切り替えました。現在は,このような方式で植生図(GIS植生図)が作られています(図-5)。
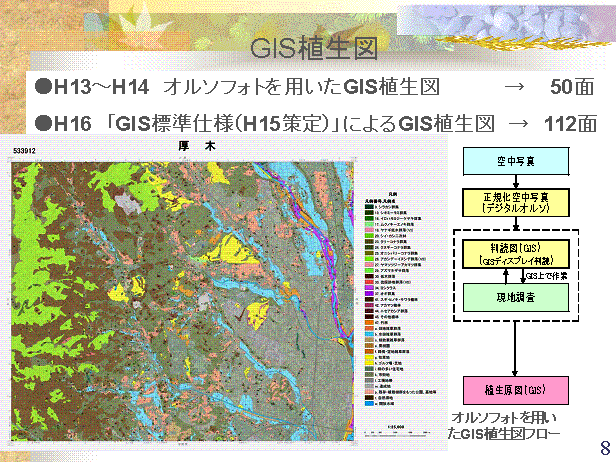
図―5 “緑の国勢調査”デジタルオルソ画像を用いたGIS植生図の作成
(提供:環境省生物多様性センタ-)
その結果,1:50,000植生図よりも位置が正確に表示できるようになり,また,多種類の小面積の群落も把握できるようになりました。植物社会学の群集・群落の分類単位で行う細区分段階でおかしいところが見つかると,優先種を分類した中区分や相観の大区分へとフィードバックして調査データを見直すことで,均一性を確保しています。また,植生図のバックデータである組成データ・優先種データ・画像データに位置情報を付してデータベース化し,管理しています。
もう一つ,測量技術が活躍している自然再生事業を紹介します。自然再生事業は,過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すための事業で,平成14年度から予算化され,現在,環境省・国土交通省・農林水産省の3省庁の8部局で取り組みが行われています。平成15年1月に自然再生推進法が施行されましたが,その基本理念は5つあり,一つが,生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り,あわせて地球環境の保全に寄与することです。二つ目が,地域の多様な主体が連携するとともに,透明性を確保しつつ自主的かつ積極的に取り組んで実施することです。地域との共同作業で進めますので,自然環境の変化状況などを具体的にきちんと住民等に説明していく必要があります。事業実施者としてのアカウンタビリティが求められることになります。三つ目が,地域における自然環境の特性,自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて,かつ,科学的知見に基づいて実施することです。地域の自然環境の科学的な把握と分析が必須です。四つ目が,自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し,その監視の結果に科学的な評価を加え,それを当該自然再生事業に反映させる方法により実施します。保全生態学で言われている順応的管理手法の適用です。このためには,確実なモニタリングが必要になります。五つ目は,自然環境学習の場として活用が図られるように配慮することです。
事業のフローは(図―6),まず,地域の自然環境を把握し,調査結果を解析します。環境要素の相互関係を整理して自然環境のどこに問題があるのかを把握し,具体的な目標像(自然再生目標)を定めます。生態系の確実な対応策はなかなか見つけにくいのですが,仮説をたてて実験を行い,それを検証していきます。これが順応的管理手法といわれる考え方で,全体の保全計画を立案し,経過をモニタリングし,結果が良ければそのまま事業を継続し,良くなければフィードバックして,事業の有効性を確認しつつ進めます。
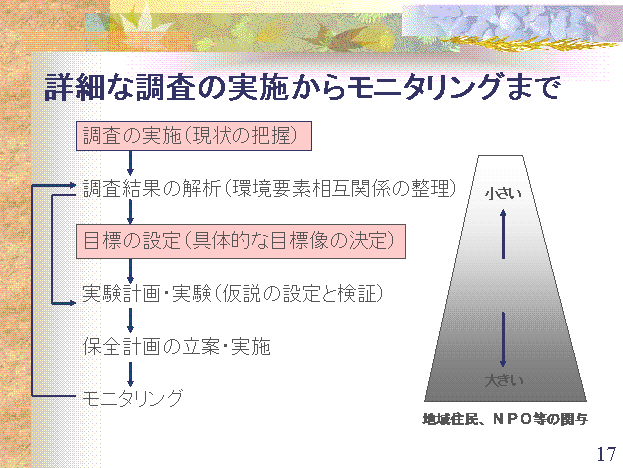
図―6 順応的管理手法による自然再生事業の流れ
(提供:アジア航測㈱)
この事業では,自然再生目標の設定が非常に重要な課題で,地域社会との合意形成を図りつつ,いつの時代まで遡って環境が再生できるかを見極めます。過去の姿を知るには,地形図・土地利用図・植生図,空中写真,地上写真,地方の史誌,衛星画像,ヒヤリングなどに依ることになります。環境情報の時空間的な把握が求められるため,高度化された測量技術が不可欠になっています(図―7)。
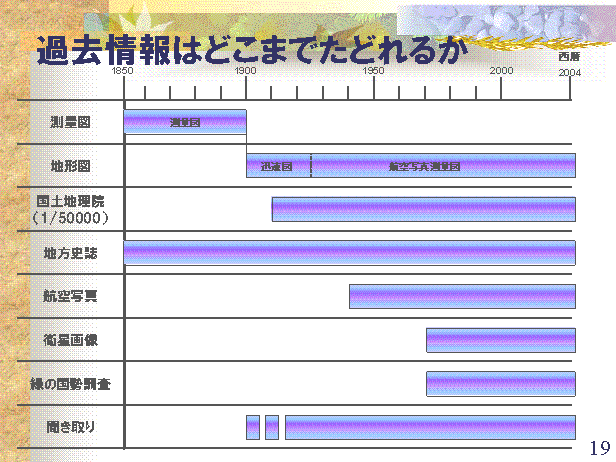
図―7 自然再生目標の設定のための過去情報
(提供:アジア航測㈱)
自然再生の一例として,サロベツ湿原をご紹介します。サロベツ湿原は,低地の高層湿原としては国内最大で,高位―中間―低位の典型的な泥炭層が分布し,それに対応した大規模な湿原植生が展開し,コモチカナヘビ,トウキョウトガリネズミ,イトウなどの北方系の希少生物が生息しています。ここが,乾燥化と笹の進入により危機に晒されています。サロベツの自然再生事業は平成10年度から始まり,湿原の時系列的な変化を航空写真を用いて解析しています。また,湿原を牧草地として開発していった歴史を踏まえ,特に農地と湿原減少との関わりを把握し,サロベツ地区を劣化させる原因がどこにあるのか,どういう問題が起きているのかといったことを図上で表わすようにしています。特に自然再生事業では,環境劣化の原因となるものを図上で抽出しながら対策を考えることが重要だと言われています(図―8)。
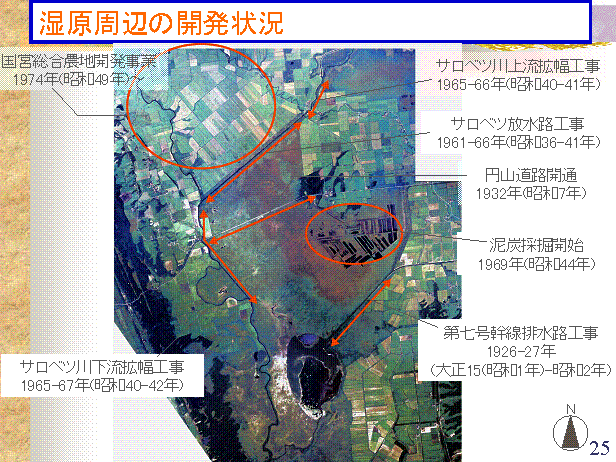
図―8 サロベツ湿原自然再生事業における,環境劣化原因の図上検討
(提供:環境省北海道地方環境事務所)
乾燥化により笹前線がどんどん湿原の方へ延びてきている状況や,泥炭採掘が広げられている状況は,時系列の空中写真を用いて把握できます。その結果から,劣化原因を整理し,サロベツ湿原再生の課題を抽出し(図―9),自然再生目標が作られました。
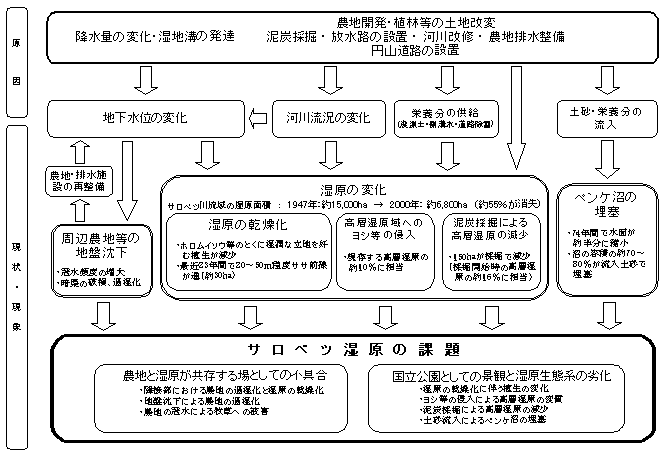
図―9 サロベツ湿原再生の課題の抽出
(提供:環境省北海道地方環境事務所)
湿原と農業の共存のために一番身近なところで,国立公園指定当時の昭和49年の状況をイメージして再生しようという整理がされます。今後,どこで,どのような保全対策が必要かという整理も図上で行います。
サロベツ湿原は非常にゆるやかな地形ですので,既存の地図では泥炭層の盛り上がりといった微地形の状況が掴めません。湿原の中には湿地溝という非常に細かい水系があるのですが,乾燥化にどのような影響を与えているかとか,地下水の流れがどうなっているかを把握しなければいけません。しかし,湿原は広大で,中はぐしゃぐしゃですから立ち入りが困難です。また,貴重な湿原の中に測量隊が侵入すると湿原を壊してしまう心配があります。そういうことが背景にあって,航空レーザ計測が使われています。ただ,問題もあります。ここに密生しているチシマザサはレーザを通さず,逆にミズゴケはレーザを吸収してしまいます。この解決は,これからの課題です。しかし,航空レーザ計測によって,湿原植生の分布や地下水の観測・調節手法の検討などが直ぐに行えるといった効果は見逃せません。
また,1964年撮影の空中写真では確認できる落合沼が現在は消滅し,現地を見ても過去に沼があった状況を知ることができません。ところが,レーザ計測データを用いて作成した赤色立体図を見ると微地形の僅かな違いから,過去の沼の存在が分かります。この沼を復元して湿原をもう一度再生しようという計画が進められているところです。また,レーザ計測では高さの精度が良いので,落合沼の修復のための水抜き水路の堰上げの基本設計に使われています。サロベツではこういった細かなデータの全てをデータベース化して,今後のモニタリングに使っていけるよう整備しているところです。
瀬戸島【司会】 元・環境行政,現・民間測量コンサルタントの立場から,自然環境の調査には測量・空間情報が不可欠だというお話をいただきました。それでは次に,研究者の立場から,原先生にお願いします。
原: 植物生態学が専門ですが,情報系の大学に所属してからリモートセンシングやGISを環境問題に適用する手法について研究しています。最近取り組んでいるのは丹沢大山総合調査です。丹沢大山は国定公園ですので,サロベツ湿原など国立公園のように国を挙げた事業ではなく,県の事業として始められました。このプロジェクトで,測量,リモートセンシング,GISなどがどのように使われているかを話させていただきます。
丹沢山地は,神奈川県民にとって大切な自然であり重要な水源地域です。また,首都圏のレクリエーションの場でもあります。豊かな自然がまだ数多く残されていますが,1970年代~1980年代に,モミ,ブナ,ウラジロモミなどの立枯れが目立つようになりました(図―10)。
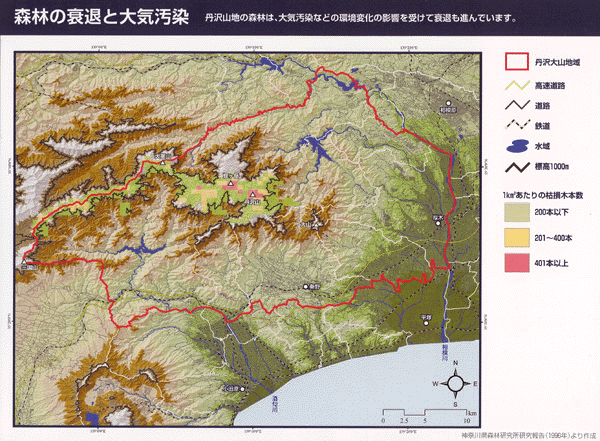
図―10 丹沢山地の立ち枯れ
(引用:アトラス丹沢 第一集 丹沢大山総合調査)
首都圏で排出された大気汚染物質が相模湾に移送され丹沢山地に運ばれて酸性雨やオキシダントが生じているとされています。また,ここはニホンジカの生息地で,戦後までの乱獲のため絶滅が危惧されるほど減りました。その後,1955年のシカ猟禁止や拡大造林により逆に増えはじめましたが,諸施策により今は安定しています。ところが,高標高地の鳥獣保護区は冬でも餌が豊富で安全なことからこの場所に集中するようになり,自然植生に強い影響を与えるようになりました。シカが下層植生を食べ尽してしまうため,ブナ林の典型的なイメージをここでは見ることができません。こういった問題のある丹沢山地を,どのようにして自然再生しようかということを目指しています。サロベツ湿原のような自然地域の再生は比較的アプローチが整理しやすいと思うのですが,丹沢山地は,ブナ林の自然地域と里山地域の両方を含んでおり,どうやって自然再生するかが非常に難しいところです。高標高域では保全強化,低標高域では環境の質の向上という形で,全体の自然の回復・再生を図るというのが県の意向のようです。丹沢山地では過去に2回の調査が行われていますが,今回の調査の特徴は,生物・水・土・大気の調査に加え,地域再生の観点から,里山地域についても再生を行い,地域全体の保全を図ろうとする問題解決型調査だということです。つまり,観光や林業の問題も含めた地域再生です。
この調査のために,水と土再生調査,生きもの再生調査,地域再生調査の3つのチームの他に,情報整備調査を行うチームが構成され,そのリーダーを仰せつかっています。自然再生には情報の共有が大事ですので,過去の調査データとともに現在の各チームの調査データを整備して,自然再生に結びつけることが情報整備調査チームのミッションです。
身近な山ですから,行政や研究者だけの判断で進めることができず,住民・NPO・行政・農林業者・研究者などが充分な意思疎通を図り,パートナーシップを築いて知恵を出しながら協議して問題解決に当たります。現状把握にとどまらず,問題解決のためには何をなすべきかという議論から個々の調査項目を洗い出し,今のところ順調にデータ収集が行われ,来年度(一部は今年度)には総合解析と政策提言を行う予定です。
このためには,各チームが調査した情報を統合して,各チームに速やかに提供する情報共有と県民に対する情報公開の枠組みが必要です。そこで,「丹沢自然環境情報ステーション
・ e-Tanzawa」 (http://e-tanzawa.agri.pref.kanagawa.jp/)
と名付けたシステムを構築し情報共有することにしました(図―11)。

図―11 丹沢自然環境情報ステーション・e-Tanzawa
(http://e-tanzawa.agri.pref.kanagawa.jp/)
「e」はelectronic(電子),environment(環境),ecology(生態)を意味します。調査チームの情報共有のためのe-Tanzawaサポート,情報基盤のe-Tanzawaベース,情報公開のためのe-Tanzawaウェブの,3つに分けています。県レベルの調査ですから,予算規模が限られていますので,効率のよい枠組み作りを心がけています。調査途中の情報の一部には公開できないものや,専門性の高いものがありますので,公開/非公開の判断をしながら行っています。また,情報の視覚化技術を駆使して,住民や議会への説明・調整等に使えるようにしています。更に,情報を1カ所で持つ必要はなく,共有さえできればよいのですから,例えば,環境省生物多様性センターとかネイチャーベースなどの外部との連携も考えています。
e-Tanzawaサポートでは,各チームの調査開始時に必要な地図を配るのを止め,ホームページから地図やオルソ空中写真をダウンロードして活用してもらうようにしました。また,掲示板を用意し,調査員同士が情報交換できる他,色々な資料もここにアップしたり,ここからダウンロードできるようにしています。e-Tanzawaベースでは,既存の色々な情報を整理しており,チームが調査したデータをどんどん格納していく仕組みにしています。調査データをなるべくタイムラグなく入力するのが最大の課題です。例えば,生きもの再生調査チームのメンバーは,現場で調査するのは専門ですが,それをデータベース化しようというところにまで力を割いてくれないという難しさがあります。そこで,データ入力の労力をなるべく軽減するため,地図データと連動させてクリックすると位置情報が拾え,そこで見つけた植物をリストから選択するだけでデータベースにスムーズに入力されるといった形のツールを作成しました。e-Tanzawaウェブは,情報をデータベース化して広く県民に発信できるように,データをGIS化して,丹沢山地のどこに植物があるのかをWebGISで表示できるようにしています。
調査の基図としては,1:25,000植生図を用いています。林業分野では,森林簿なども利用しています。自然系と林業系では凡例区分が異なるのですが,良い所取りをするようにしています。また,イコノス高分解能衛星データは樹木の1本1本まで分かりますので,植生図よりももっと細かな情報が必要なチームに提供するようにしています。調査結果を地図上に面として表示するには領域を括りますが,これが大変だったので,領域分割の線引きを自動化するようにしました。
e-Tanzawaには,丹沢の現況を知ることができるアトラス丹沢などが公開されていますので,是非ご覧下さい。
2.これからの環境事業に求められる測量の役割は?
瀬戸島【司会】: 環境と測量の関わりを,わが国にリモートセンシングが導入された頃から時系列で見ていくと,物珍しさの時代(70年代)から,模索の時代(80年代)を経て,有用だがうまく使えない時代(90年代),そして,ようやく使える時代(2000年代)になったと理解しています。ようやく使える状態というのは,データ面では,地域環境レベルの調査ができる精細なものが出始めてきたことや,時系列的なデータ整備が進んできたことが背景にあります。また,ハードやシステム面では,操作が容易で,価格も手頃になり,身近なツールとして専門家以外でも使えるようになったことです。現場で集めた環境調査データを現場でデータベース入力できるようにもなってきました。また,時空間的な解析を行うGISがかなりよくなり,リモートセンシングやGISの大学教育も充実し,そういう教育を受けた,GISを使いこなせる環境技術者が増えてきたことも背景にあります。測量が環境分野で,今まで以上に貢献するための素地・土壌が熟してきたと考えています。
一方,環境調査はローテクでいいんだと言う神話みたいなものがあり,新しい計測機器に対してアレルギーを感じる人が多いのも現実です。ローテクが美徳だと感じている環境技術者さえいます。でも,時の流れによって,現場作業もフルデジタルでやらなければいけないようになってきたので,少しは改善されてきたと思いますが,まだまだです。測量の人たちが環境調査の分野で活躍するようになると,専業の環境コンサルタントのサポートができ,調査の客観性と効率性が高まると思うのですが,この辺も含めて議論したいと思います。
まず,地域の測量会社はどのような環境の仕事をしているか,および,今後したいと考えている環境の仕事は何かの実態を見てみたいと思います。日本測量協会主催サーベイアカデミーの環境講習会に参加した測量会社の方々にご協力いただき,アンケート調査した結果があります(図-12)。
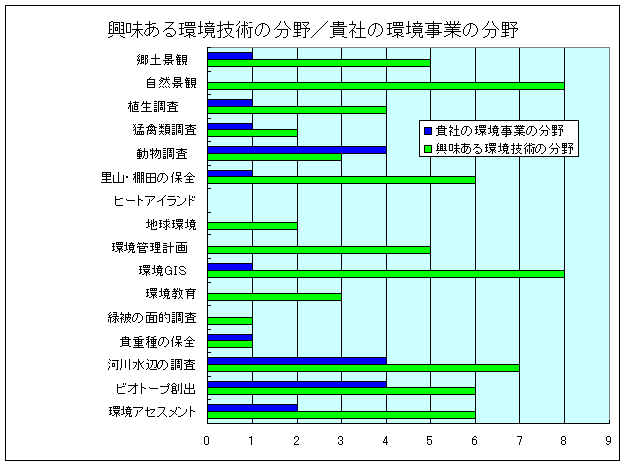
図―12 地域の測量会社のアンケート調査結果
これによると,動物調査,河川水辺の調査,ビオトープなどに取り組んでおり,自然景観,里山・棚田の保全,環境GIS,河川水辺の調査,ビオトープ,環境アセスメントに興味を示しています。地域に特化した環境問題に取り組んでいるか,取り組もうとしていることが分かります。川窪さんや酒巻さんは,現在,地域の環境コンサルタントとして活躍されていますが,地域における環境事業で求められる測量の役割について,どのようにお考えでしょうか。
川窪: 大分県には環境配慮推進要項という規制があります。これは,法アセスや県のアセス条例にのらない類のもので,事業規模や事業対象は限定されますが,環境に配慮した公共工事が求められていることから,環境調査業務が設計段階の調査と絡めて発注されます。
酒巻: 紹介されたサロベツ湿原や丹沢は,基本的な環境情報を,国や地方自治体が中心になって,住民とともに整備しようという流れだと思います。一方,地域の測量会社が携わる環境の仕事は,どちらかというと個別のレベルだと思います。個別の調査は比較的多くの件数が発注されるので,測量会社は受注面で注目しています。長野県の場合,最近増えてきているのが,公共工事を行う前の,個別計画の段階で環境調査が行われることです。例えば,猛禽は里山地域にはいないのが不思議なくらい,ある程度の半径の中に必ず出現しますし,少し奥に入ればクマタカが生息しているのは当たり前です。そうすると,出現の度に揉め事になって,何年もの間,調査ばかりやっているということになります。ここ数年,工事計画の度にこの類の環境問題が発生し,散々痛い目に遭ってきていますので,この反省から,最近は,事前に環境調査を行うようになったのだと思います。
ここで問題になってくるのが,国や県が整備している環境情報と個別計画の環境調査で行われるものは,基図の縮尺が違うだけでなく,内容的にも関連していないことです。極端な言い方をすると,国や自治体が整備した環境情報が個別計画の調査には使えません。環境情報は一つでなく,色々な用途の色々な種類がありますので,その辺をきちっと組み立てていかないと,環境情報を間違って使ったり,悪用する人が出てくるかもしれません。これまでの失敗は,全国レベルの把握を目的として整備された環境情報を用いて,個別レベルの環境問題も押し切ってしまおうとしたからだと思います。環境情報やGISがよく使えるようになってきたので,環境情報の整備の仕方や,使い方をもう少し考えないといけない段階かなと思います。
瀬戸島【司会】: 例えば河川改修の計画時に,ちょっと植生調査をしてくださいと頼まれると,費用的にも限りがありますので,その場限りの調査をしてきました。現実に起こっている環境問題の解決には,それでよかったのだと思います。しかし,これからは,ある程度の面積規模で整備される標準的な環境情報と,個別に行われる環境調査のデータとがお互いにリンクするようにしなければならない時代になってきたのではないでしょうか。これまでの測量技術者は仕様遵守型の業務に慣れ,問題解決のための要求仕様を測量技術者が作ってこなかったことが,今後の大きな課題になるような気がします。問題解決のための仕様作成を提言できる測量技術者が必要になってくるのではないでしょうか。
酒巻: 河川調査では,住民がインターネットを使ってデータ入力できる市民参加型の河川情報システムが作られています。これに参加できるのはITに抵抗のない人に限られてしまいますが,そういうことが可能になっていることが非常に大事だと思います。丹沢の例では,現地調査チームのメンバーがリアルタイムで入力できるようになっているようですが,ある決められた人だけがデータを作るのではなくて,住民もデータ入力ができ,また,住民がその情報を保管していくシステムが機能すると,環境情報の信頼性が高まっていくのではないでしょうか。
原: 丹沢山地のWebGISは双方向で情報共有できるようにしていますが,情報整備チーム側からは基本的な情報を提供し,現地調査チームは調査結果を提供するという形で運用しています。丹沢大山総合調査とは別に,NPOを中心とする県民参加型の事業が進められており,植物や動物の確認や水質などのデータが情報共有化されているようです。いずれ,それらのデータもe-Tanzawaシステムに乗っかる仕組みを作る計画です。ただ,県民参加型で集められるデータは信頼性に欠ける可能性がありますので,データベース化の際には,スクリーニングをきちんとしなければならないと考えています。
瀬戸島【司会】: 住民参加型で環境情報を収集・共有化できるツールが,かなり出来てきたと思います。動植物の種や属の同定といったことは難しい面があろうかと思いますが,少なくとも,どこで見つかったというような位置に関する情報は,GPSを使えば,以前よりもはるかに正確に得られます。最近の計測ツールの進歩は目覚しく,また,結構使いやすいものが出回っておりますので,住民参加型で環境調査を行う環境が整ってきたのではないかと考えています。
赤土: 今,自然環境保全のための測量技術が必要になっています。リオデジャネイロの環境サミットで初めて,生物多様性という言葉が出てきました。生物多様性の概念の中には,種の保全,生態系の保全,遺伝子という3つの要素が含まれています。このうちの生態系の保全は,それまでは,地域の中の優れた自然とかが対象だったのですが,この時から,トータルな環境の質を求められるようになったのです。これにより,生態系を理解するため,地球規模から地域規模まで,空間的な総合解析が必要になりました。この解析のためにはデジタル化が必要で,これが,環境と測量との関わりにおいて大きな転機を迎えることになったと思います。個々の環境も大事ですが,総合的な地域環境の把握が,今,必要な時代になってきていると思います。
瀬戸島【司会】: 生態系の空間的な総合解析のために測量の果たす役割が大きくなるということですが,一方で,環境分野に進出したいと考えている地域の測量会社は,自然景観,里山棚田の保全,環境GISなどに高い関心を示しています。こういうことを踏まえて,地域の測量会社の貢献が期待される,今後の注目すべき環境事業にはどのようなものがあるか,月刊『測量』2006年の新年号でもありますので,占っていただきたいと思います。
原: 少子高齢化の時代の国土をどうすべきかということと併せて環境問題を考える時期にきていると思います。これまでの環境事業は,場当たり的な開発に対する環境アセスメントの繰り返しだったように思うのですが,今後は,もう少し大きな時代の流れに即した全体の青写真をきちんと描き,戦略的環境アセスメントともいうべき,基本的な環境情報を整備した上で,地域レベルの自然環境の問題を位置づけることが必要ではないでしょうか。既存の環境情報が効果的に利用されるようになり,環境調査の重複も無くなり,調査に費やされる経費の削減にも繋がっていくと思います。地域レベルの環境情報の整備は,地域の事業者が参画して行うのがよいと思います。地域住民から里山をどうしようかという課題が出された時には,ここにこんな環境情報があるよと出してきて,こんなことが出来るのではないかという計画が立てられるような枠組みができれば,納税者としても納得のいく結果が導き出せそうな気がします。
瀬戸島【司会】: 環境の観点で言えば都市と里山とは一体不分離であり,里山の環境を良くすれば都市環境も改善されます。ところが,都市部の都市計画区域・市街化区域では1:2,500地形図などの都市的な情報が整備されているのに,市街化調整区域の一部や都市計画区域の外側にある里山は情報の空白地帯なのです。時には1:25,000地形図を拡大して使っていたりして,都市域とは驚くような差があります。これからの里山保全を考えるとき,情報整理は重要ですので,戦略的に整備し活用していく必要があると思います。ただ,今までと同じ方法で,長い年月をかけて作るという時間的余裕は許されないので,効率的かつ高精度の時空間データを整備しなければいけない。そこに,地域の測量会社が活躍する場があるように思っています。
酒巻: 自然環境は,未来展望を明るい方向へ持っていくための一つの財産です。その財産を守るため,国はレッドデータブックを作りましたが,都道府県や市町村レベルでは未だ手つかずのところが残っています。そういう所では,貴重な動植物がどんどん消えてしまっています。今ならまだ間に合うかもしれないので,今やらなければいけない。GISを使って環境情報を全体的に整備して解析することも大事ですが,それだけでなく,同時進行で,きちんとした環境データを作らないと拙いことになります。これが,環境の現場に携わってきた私の主張です。両方を同時にうまく進めることが必要で,どちらかに偏ってはいけないと思うのです。
原: 環境保全計画のために必要な地図の縮尺は,目的や規模によって違うということも考えないといけないと思います。植生図について言えば,全国レベルだと1:25,000でよく,これを1:2,500で揃えようというのは無理な話です。また,地域によっても環境に対する見方や重要度が変わることを考えないといけない。私は千葉に住んでいますが,都市化が進んでいますので,近郊の雑木林が非常に貴重な自然なのです。ところが故郷の東北では,雑木林がごく普通に存在し,貴重なのは山奥にある自然性の高い林だということになります。それぞれの地域で生態系に対する見方が違いますから,これを整理する必要があります。
また,生態系を保全するためには生態系の上位概念であるランドスケープをユニットにしないと生態系同士の関係をうまく捉えることができない。ランドスケープで全体の環境を把握した地図を作る必要があるのではないかと思っています。
瀬戸島【司会】: どんな事業が注目されそうかというところでお話を伺ってきましたが,戦略的な環境情報整備を推進しなければいけないということが,時の勢いを背景にして,これからの環境事業として占えるかなと思います。
また,個別の環境調査は,言わば局所的な環境情報ですが,好き勝手な方法で野放し状態の調査をするのでなく,その調査結果が他の目的にも使えるように,よりマクロな標準化された情報に組み込むことが必要です。このためには,少なくとも位置的な保証が大事で,この部分は既存の測量技術を活用すれば実現できると思います。 地域の測量会社で,こんな環境事業を考えているとか,環境にこういう事業があるんじゃないかとか,そういうご意見はないでしょうか。
川窪: 一例ですが,大分県内に水資源が枯渇して地下水が非常に乏しい地区があります。ボーリングデータが必要なのですが,個別案件ごとのデータが存在するだけですから,せいぜい市町村単位でしか把握できません。大分県下という大きな地域の水管理をしようとしてもデータそのものが公開されていませんし,個別案件のデータ数も充分でなく,しかも,分散しているため,補完するための新たな調査が必要です。現地調査が伴いますから,測量会社にとってはうってつけの業務です。同じように,その他の自然環境要素の調査や,自然環境以外の環境調査も必要ですから,地域環境の把握のために各種の基本的な環境データを整理して,共通化・標準化して整備し,環境情報を流通させることが必要です。調査を調査として終わってしまうのではなく,調査したデータを利活用できるように編集することが重要なので,測量技術者の力が必要になってくると思います。
瀬戸島【司会】: 先日,久しぶりに熊本へ行ったのですが,里山にものすごい勢いで竹林が拡大していました。一般の人にとっては竹林も緑であって,山が禿げたわけではないので危機感を持ちません。でも,生態系の観点でみると大問題だろうと思うのです。このような自然環境の変化に対しては予算執行も充分でないのですが,放ったらかしにしておくと大変な状態になると思います。こういう現象の時系列的なモニタリングも,今後の事業に育っていくのではないでしょうか。
また,地域環境問題というと砂漠化や地球温暖化を連想し,測量とは別世界の大きな話になってしまいますが,去年から今年にかけて数多く襲ってきた台風が地球環境の変化に依存するものとすると,地球環境と地域環境とを分けて考えてはいけないと思うのです。そこで,地球環境に絡むもので,測量が活躍できる環境事業を占っていただけないでしょうか。
赤土: 地球環境で大きな問題になっているのはCO2です。林野庁が中心に進めていますが,森林バイオマスによってどのくらいCO2が吸収され固定されるかという測定が行われており,バイオマス量の計測に測量技術,特にレーザ計測が効果をあげています。地球環境の問題といっても,その原因は地域から始まるのです。地域レベルで森林をどれだけ保存するかということになるのですが,考え方は地球レベルで行うということです。
瀬戸島【司会】: CO2削減は京都議定書の約束で,90年が基準になりますので,その当時の森林の姿を記録した航空写真を利用した全国的なデジタルオルソ画像の整備を国が進めています。また,都市の中の公園や樹林などのCO2吸収量を計測するための調査手段として空間情報技術が利用されています。
酒巻: 地球温暖化は,森林だけでなく,地域の様々な問題との関わりがあります。生活に密着したところでは,生ゴミの消却時にCO2をできるだけ出さないよう,ガソリンを使わないようにするとかです。農業を例では,畑の位置ごとの土壌分析を行い,それに見合った施肥や耕作を行うことで無駄の無い,環境にやさしい営みができます。これまではかなりアバウトに行われてきたのですが,これからは,時系列的なデータ管理が行われ,きめ細かな対応が求められるようになると思います。それには,時刻と位置座標をもった時空間の環境情報として蓄積・管理されていくことが必要です。
瀬戸島【司会】: 都市のヒートアイランドの問題については,熱的現象の把握には以前からリモートセンシング技術が用いられてきました。今,その対策として,物理的・工学的なパラメータを用いたアプローチや屋上緑化などが行われています。ヒートアイランドが問題になるような都市域には建物が密集し,昔の地形が分からなくなっているのですが,レーザ計測すると,埋蔵されてしまった昔の浅い谷地形が浮き彫りになって見えることがあります。地域本来の地形が分かると,風の道を探ることができます。そうすると,ドイツで行われているような,ヒートアイランド現象を軽減する風の道にも配慮した都市計画を立てることができるのではないかと思います。また,風の道マップのようなものを作ると面白いかもしれません。
原: 今はどこにでも人が住んでいますが,昔の人は,このような地形のところに自然災害が発生するから住まなかったということが分かっていますから,昔の地形が分かると,防災面でも有効ですよね。このような自然立地の評価にも適用できるような環境情報が整備できるとよいと思います。
瀬戸島【司会】: 山林が荒れているという問題があり,山林を維持管理していくための財源として,あちこちの県で,独自の森林環境税とか水源環境税を設定しています。各世帯から年間数百円を数年間,徴収するものです。この財源は山林を整備するためのものですから,それ以外の目的に使われることはありません。山林の維持管理に効果があり,この財源を真に活かせる,測量技術を活用した施策の提言ができないものでしょうか。単にあれをやりましょう,これをやりましょうというのではなく,少し大きな目標を持った政策ビジョンでないと受け容れてもらえないと思います。政策提言というと,2004年のISPRS(国際写真測量リモートセンシング学会)ではリモートセンシングを用いた政策提言の部門が追加されていました。これからは,測量でも,政策提言を身近に感じるように努力しないといけないのではないでしょうか。
赤土: 地域環境の点では,ある程度まとまりのある地域ごとの環境保全対策が必要です。特に,水の問題は,流域単位で環境情報を整理して対策を検討する必要が出てきました。農業用水路の総延長は河川の3倍あると言われており,河川だけではなく,この水路をどのように位置づけて,流域全体の環境をどのように保全するかを考えなければいけません。この対策の検討のためには,個々の市や県を超えた流域全体の自然のメカニズムを知る空間情報が必要不可欠です。
平成18年度予算要求に盛り込まれた生態系ネットワークは,各省が取り組んでいます。これは,生物の生息空間であるハビタット(ビオトープ),生物の生息地間を結んで生物が連続移動できるネットワーク化されたコリドー(緑の回廊)で構成されます。全国レベルの考え方もあるし,地域レベルもありますが,地域全体の健全な自然環境を保全していこうという考え方が根底にあります。これには,時間と空間の両面から捉える必要がありますので,時空間データベースが必要で,地域性の強い技術領域だと思います。
瀬戸島【司会】: これまでにお話いただいた中から,環境事業のために期待できる測量技術を,私見を交えながらまとめますと,3つほどあると思います。一つは,デジタルデータのハンドリングで,環境情報を作るためにも,環境情報から環境を評価するためにも,今後は重要になります。やがて,広い範囲の環境情報をフルオートで収集・処理することも考えられると思います。二つ目は,データフュージョンの利用技術です。違うもの同士のデータを重ね合わせて使うことは今までもやっているのですが,これからはもっと進んでいくと感じています。三つ目は,双方向情報コミュニケーションができるWeb-GISの利用です。例えば,植生の専門家と農業の専門家と地形の専門家が同じデータを一緒に見ながら検討を進めることができます。
酒巻: 新しい測量技術を環境分野で活用するアイデアが大事ですよね。例えば,モバイル携帯電話が作られた時に,今のように多様な使い方をすることを読み切って開発したのではないと思うのです。物が出来上がってから,皆がこういうことにも使えるのではないかとアイデアを出し合ったのだと思います。GPSも同じだと思います。GPSは,衛星に高精度の計時システムを搭載し,地上受信機の位置座標を求める機能だけなのです。相対測位やキネマチックなどの方法は,あとから考え出されたものです。同じように,環境についても,色々な新しい機器をうまく使いこなす発想が大事だと思います。
川窪: 酒巻さんの話につなげてCADの例を挙げますと,これの基本機能はドラフターなのですが,ソフトがどんどん開発され,色々な使い方ができるようになっています。GISも地理データを扱うツールに過ぎませんから,色々とアイデアを出して使いこなしていけば,日常業務や生活の場でも普通に見られるツールになると思います。要は,使い方次第です。
環境という捉えどころのないものを見えるようにする可視化技術は,評価のためにどのように単純化するか,モデル化するかという技術と理解しています。環境の可視化は,アメリカで先進的に行っており,日本環境アセスメント協会でも研究を始めています。混沌(カオス)とした定性的な環境を,皆が共通理解できるように,いかに定量化するかの技術が大事です。定性分析は日本の測量分野には無い考え方ですが,化学の分野ではよく使われています。それは何で,どれくらいあるかということを分析するものですが,この技術を測量技術の中に組み入れ,混沌としたものを理解できるようにすれば,新しい測量技術に結びつくのではないかと思います。
赤土: デジタル化によって,位置情報に再現性を持たせたことが非常に大きな力になっています。昔からある紙に印刷された植生図を現地に持っていっても,どこにいるのか分かりませんでした。ところが,植生図がデジタル化されたお陰で位置が再現できるようになり,環境アセスメントにも活用できるようになるなど,その位置再現性が,利用可能性をすごく広くしたことを評価しています。
川窪: 測量技術者は現場作業ができるというのが,一つのポイントだと思います。これまでの測量業務は,基本的に現地で解決していくものでした。リモートセンシングが有用な技術であっても,グランドトルースという現地確認が必要です。測量が環境分野で活用されるようになっても,現地での実証が必ず必要です。地域の事情に通じた地場の測量会社の,活躍の場の一つではないでしょうか。
原: 位置をきちんと押さえる測量技術に時間軸が付与され,色々な環境要素の挙動を時空間で把握できるようになったので,測量の利用可能性が大きく広がりつつあると思っています。スケールについても,レーザ計測によりセンチメートルの単位からグローバルなスケールまで扱えるようになりました。ここでの課題は,主体をどこに置くかによって環境は変わることです。環境のとらえ方のひとつに主体-環境系というのがありますが,どの主体をターゲットにした環境問題なのかを明確にしないといけません。人間が主体になることが多いですが,主体を明確にした上で問題を考えると,うまく整理ができるのではないかと思います。デジタル化され,予測・評価のモデル化・抽象化が行われると,結果の裏付けが補強されます。そうすると,現場調査をした人のノウハウが入った取り纏めができると思います。やはり,環境の問題は現場を知っている方が一番だと思いますので,測量の役割は,その方々をサポートするのに必要なデータを提供することです。測量データの限界を認識した上で,最大限に利用するというのが鍵かなと思っています。
3. 新しい時代の環境測量技術者を求めて
瀬戸島【司会】: 測量分野の人たちが環境分野で従事できるように,環境のわかる測量技術者を育成するにはどうしたらよいでしょうか。環境に明るいでもいいのですが,単に測量というだけではなく環境という冠の付いた技術者の育成をどうすべきかということです。今まで道路測量を行っていた人が,そのままの気持ちで環境分野の測量をするわけにもいかないと思います。
原先生の大学は,空間情報と環境の両方をやっておられますが,環境分野の測量技術者という視点での人づくりについてお話いただけませんでしょうか。比喩的な表現をしますと,測量と環境の二つの車輪を持った二輪車は,前後で同じ大きさの車輪が必要なのか,あるいは,測量という車輪が少し大きいほうがよいのか,それとも,車輪の大きさはどうでもよいのかといった視点で,どういう教育をされているのか,お話しいただけますでしょうか。
原: 情報は,何かの分野に役立てないと,ただ,そこにあるだけで,有効にはなりません。そこで,私どもの環境情報学科では,自然環境や社会環境を対象とした情報教育をしています。とはいえ,理想と現実には乖離があります。環境問題は非常に広い範囲を含んでいるにもかかわらず,大学で扱える環境の範囲には限りがあるため,自然環境GISなどのように,ある程度,特化した内容の教育を行っています。
道路や河川などの土木の分野では,環境に配慮した設計・施工が求められますから,そのような現場の第一線で活躍されている人は環境問題を真剣に考えておられ,環境に配慮できる土木技術者を育成されています。測量会社のアンケート調査結果を拝見しても,環境問題に強い関心を示しておられることが良く分かります。ですから測量業界でも,環境配慮などで苦労されている現場の技術者の教育が大事ですから,日本測量協会のような機関が,「環境測量」という教育講座を設けたらいかがでしょうか。
瀬戸島【司会】: 重要なことで,「環境に明るい測量技術者になるための基礎技術講座」といったシリーズ講座を日本測量協会で開催してほしいと思いますね。
赤土: 測量技術者と環境技術者の技術的連携は,会社で一番の課題になっています。現在の航測会社が環境や防災の業務を行っているのは,元はといえば,測量の延長線上で環境や防災のための航空写真や地形図を作製してきたからです。今では,リモートセンシング,GIS,レーザ計測などの測量技術を活用する環境コンサルタントとして成り立っています。つまり,測量技術を使って環境問題をコンサルタントするというのが特色になっています。
そこで課題になるのは,測量の担当技術者はレーザ等新しい計測技術の習熟と計測精度の確保に一生懸命で,目的である環境の理解が進まないことです。ですから,環境技術者の方から,こういことはできないだとうかとか,レーザ計測で湿原を調査すると精度はどれくらいまで取れるとか,そういうことを具体的に相談するようにしています。残念ですが,測量側から環境問題についての提案は殆ど出てきません。これが現状ですので,できるだけ技術者の連携,技術の融合を図ろうとしているのですが,なかなかよい案が見つからない状況です。
瀬戸島【司会】: 私も航測会社に身を置いていますが,同じような状況です。でも,原先生のところのような教育を受けてきた卒業生は,あまり,測量と環境との間に塀を作っていないように思います。両方の目を持った人が,少しずつ増えてきていると思います。ところが,会社に永く身を浸してきた人は高い塀を作ってしまいがちですので,その世代の人達の間のディスカッションや,発想の転換が必要なのかも知れません。会社内でも,測量から環境へという一方向だけでなく,環境から測量へという方向もあって,相互乗り入れができればよいでしょうね。測量と環境の技術者の連携・技術融合の過渡期にあるという感じでしょうか。
川窪: 地域の中小コンサルの場合,調査計画から環境評価に至るまでの全ての業務をカバーできるスーパーマンにならないといけません。全ての業務を抱えなければならないというのが現実です。環境分野のターゲットが広すぎるため,その全てが分かるジェネラリストの部分と,ある分野の専門性が高いスペシャリストの部分の,両方を持ってないといけない。しかし,現実にはスーパーマンに成るのは不可能なので,求められている総合力を発揮するための専門技術力とのバランスをいかに保っていくかということだと思います。全ての分野の専門家である必要はないので,例えば,測量という自分の得意分野を確立し,その上で,環境にも幅広い知識を持って業務に当たることが良いように思います。
また,測量を学んできた人達は,化学や生物学が苦手で,アレルギーさえ持っている人が多いようです。自然生態系というのは,突き詰めれば,実は生化学的な反応の積み重ねなのですが,そのことが分からないと,生態系の本質の理解ができないと思います。このことから,環境情報の学問を実践している大学教育のカリキュラムには,植物学,化学,地学も盛り込んでいただき,ある程度のオールラウンドプレーヤーを育てていただけるとありがたいところです。
瀬戸島【司会】: 基本図や台帳といった測量をメインにしてきた人であっても,環境市場のニーズが増えれば,それに応じられるように,ある程度の専門分野のシフトが必要になります。これを可能にする再教育を大学でやっていただけるとよいですよね。
他の例ですが,文化財測量の世界では,遺跡・遺物が作られた当時の時代背景を理解しないで測量した成果を文化財研究者や学芸員に見せると拒絶反応にあいます。測量技術者にも文化財の理解が求められているのです。測量技術者が文化財の知識を吸収したい場合には,例えば,奈良大学通信教育学部の文化財歴史学科などを利用できます。同じように,環境測量でも再教育の仕組みがあるとよいと思っているところです。
赤土: 植生調査で気になるのは,植生の判読技術者がきわめて少なくなっていることです。植生調査の入札に対応できる業者が限られています。大学でも育成してくれませんので,測量コンサルタント側で育成しなければいけません。これが,非常に大きな課題になっています。
原: かつては沢山あった理学的な植生学研究室が,どんどん少なくなりました。ところが最近,保全生態学とか応用面の必要性がさけばれるようになって,そういう研究室が少しずつ出てきて,現場の植生が分かる人を育てる学科や研究室が一時よりは増えています。そういう教育を受けた卒業生を,測量・環境コンサルタントで是非採用していただき,裾野が広がることを期待したいと思っています。
瀬戸島【司会】: 新しい時代の環境測量技術者を求めて,ということに関して,まとめの意味も含めて,ひとりずつコメントをお願いします。
酒巻: かつての測量技術者は,測量だけをやっていればよかったのですが,環境と測量が技術融合するようになると,環境の調査・分析・評価などの業務を一通りやらなくてはいけない。それに加え,政策提言や市民のとりまとめ,場合によっては子ども達の環境教育やマスコミ対応もやらなければならない。扱う測量技術の概念もジオマチックスや空間情報工学のように変化し,技術領域が広がっています。このことを考えると,測量の狭い技術領域や低い社会的地位という,一般に理解されている測量技術の認識を改めないといけないという気がします。いっぽうで,測量技術者も総合力を持つことが求められると思います。
川窪: 私はプラント,地方行政,環境コンサルタントという違う世界を歩んできましたが,その経験から,違う分野には非常に面白い技術が転がっていると思います。測量の世界でも同じだと理解しています。そのような技術を,いかに違う分野の技術と融合させるか,技術のフュージョンやハイブリッドによって,測量技術に新しい風を吹き込めるのではないかと思います。こういうことを実践できる測量技術者が,これからの時代に必要なのではないでしょうか。
赤土: 測量技術者はこれまでは計測だけの世界にとじこもってきたのではないでしょうか。ところが,レーザ計測のような計測技術は,非常に広い,違った分野で応用可能です。これまでは,環境技術者側からの要求を受身でやってきたのですが,これからは,測量技術者の方から,技術の利用分野を拡大させるという姿勢が必要だと思います。
原: 環境分野では,市民やNPOの力が非常に付いてきました。測量やコンサルタントの本当の力量が問われる時代になったと思います。技術動向を踏まえるのは勿論,市民との対話やニーズの吸い上げによって,社会が求めているものを解決する提言ができる技術者でないと生き残れません。このことに,各企業がどういう形で対応していけるかというのが鍵だと思います。WebGISを介して色々な環境情報が公開されると,市民の目が行き届くようになりますから,より一層,力量が問われると思います。
瀬戸島【司会】: 環境の本質は問題解決だと思っています。ですから,その世界に入った測量技術者は,当然,問題解決型の環境測量技術者になっていかなければならない。環境測量コンサルタントという名がよいかどうか分かりませんが,その技術体系を整備し,それに則った環境測量技術者の育成ができないでしょうか。これからの測量技術者は,環境というような冠言葉の付いた技術者が認知される時代になると感じています。
本日は,長時間にわたりご討議いただき,ありがとうございました。
【ご出席の皆様のプロフィール】
| ■ 川窪一郎 | ||
 |
本来はプラントが専門で,旭化成工業㈱や㈱いすゞ中央研究所で環境化学を専門とした後,宮崎県佐土原町役場で公害・環境保全行政や生活排水対策総合基本計画の策定に携わり,民間環境コンサルタントに転出して今に至る。現在は,大分県・宮崎県を拠点にして,多自然型河川計画,自然環境調査,環境計画,環境配慮型設計,GISによる環境解析などに従事している。 | |
| 【資格等】 技術士(環境部門,建設部門),公害防止管理者(大気,水質),環境マネジメントシステム審査員補,環境カウンセラー(事業者部門)など | ||
|
|
||
| ■ 酒巻裕三 | ||
 |
民間の測量建設コンサルタントで長野オリンピックの環境影響評価の責任者を務めるなど,環境業務に従事した後,独立。環境はまず現場からを実践しており,長野県を拠点に,市町村の環境計画コーディネータや市民の環境保護活動,企業の環境経営支援,子供達の環境教育など,ユニークな活動を行っている。 | |
| 【資格等】 技術士(総合技術監理部門/建設-建設環境,建設部門/建設環境,河川・砂防及び海岸・海洋,環境部門/自然環境保全),環境カウンセラー(市民部門,事業者部門),環境省こどもエコクラブ応援団,長野県科学教育振興検討委員,長野県希少野生動植物保護監視員,長野県自然保護レンジャー,長野県自然観察インストラクター,長野県ISO14001推進員,長野市自然環境保全推進員,エコアクション21審査人,他 | ||
|
|
||
| ■ 赤土 攻 | ||
 |
厚生省(国立公園局)に入省後,環境庁の阿蘇九重国立公園管理事務所,南関東地区国立公園・野生生物事務所,新宿御苑管理事務所などの所長を歴任。その後,民間の航測会社で測量技術を活用した環境事業を実践している。また, (社)自然環境共生技術協会の立ち上げに尽力した。 | |
| 【資格等】 技術士(環境部門/自然環境保全,建設部門/都市及び地方計画) | ||
|
|
||
| ■ 原慶太郎 | ||
 |
植物生態学、景観生態学が専門。情報系の大学に籍を置いてからリモートセンシングやGISを用いた自然環境保全の研究を行っている。大学では,環境情報論,環境保全論等を担当。 | |
| 【資格等】 理学博士(東北大学),(財)自然保護協会理事,千葉県環境審議会委員,千葉県景観等影響評価専門委員,佐倉市総合計画審議会委員,ちば谷津田フォーラム副代表,他 | ||
|
|
||
| ■ 瀬戸島政博 | ||
 |
民間の航測会社に籍を置き,リモートセンシングや空間情報技術を用いた環境事業を専門とする。昨秋,空間情報技術を利用した里山林の樹種区分の研究により,九州大学から博士(芸術工学)を授与。 平成14年から2年間,東京大学生産技術研究所の客員教授を務めた。現在,本誌の編集委員会副委員長。 |
|
| 【資格等】 博士(工学:長崎大学),博士(芸術工学:九州大学),技術士(環境部門,建設部門,林業部門,農業部門,情報工学部門,応用理学部門,総合監理部門),測量士,空間情報総括監理技術者,東京農工大学農学部 非常勤講師,東京大学生産技術研究所研究員,(社)日本写真測量学会副会長,など。 | ||